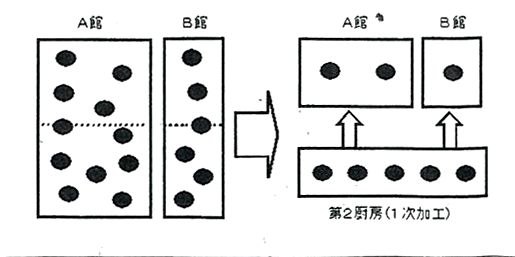|
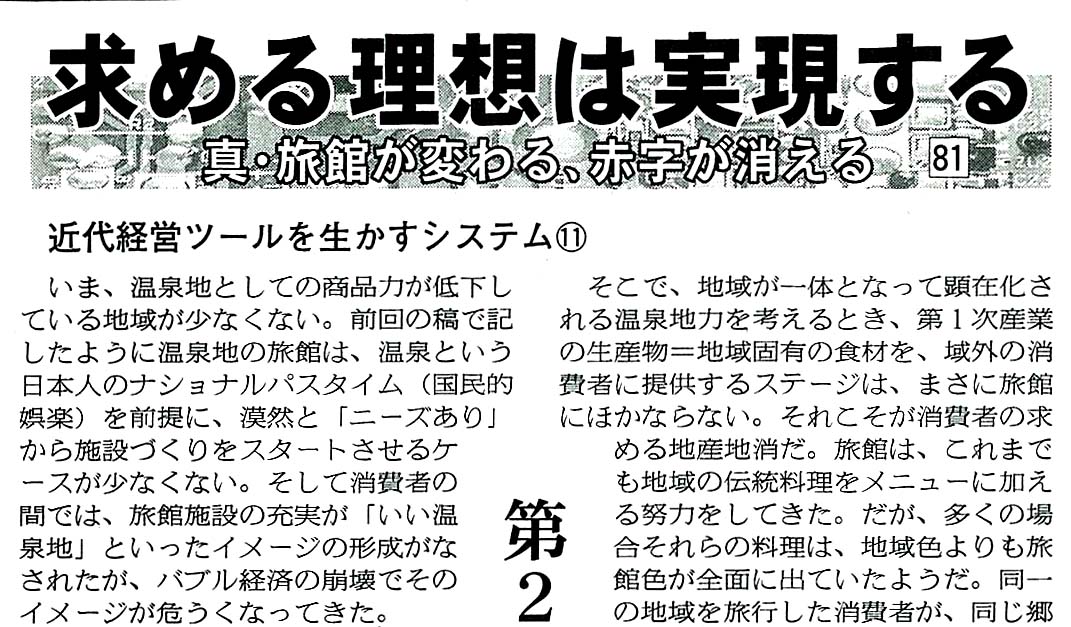 いま、温泉地としての商品力が低下している地域が少なくない前回の稿で記したように温泉地の旅館は、温泉という日本人のナショナルパスタイム(国民的娯楽)を前提に、漠然と「ニーズあり」から施設づくりをスタートさせるケースが少なくない。そして消費者の間では、旅館施設の充実が「いい温泉地」といったイメージの形成がなされたが、バブル経済の崩壊でそのイメージが危うくなってきた。 いま、温泉地としての商品力が低下している地域が少なくない前回の稿で記したように温泉地の旅館は、温泉という日本人のナショナルパスタイム(国民的娯楽)を前提に、漠然と「ニーズあり」から施設づくりをスタートさせるケースが少なくない。そして消費者の間では、旅館施設の充実が「いい温泉地」といったイメージの形成がなされたが、バブル経済の崩壊でそのイメージが危うくなってきた。
このことは、元来あったはずの「温泉地力」を軽視した結果といえなくもない。辛辣にいえば、温泉地力を度外視して施設展開に狂奔したツケともいえる。温泉地力とは、旅館だけで形成されるものではない。地域の第1次産業をはじめ2〜3次産業が一体となって形成されるものだ。
例えば、昔から「その土地の料理を食べたい」「どこへ行っても同じような料理」「山の中でマグロの刺身はいらない」といったセリフが言い続けられてきた。だが、はじめに施設ありきの旅館では、「これが旅館料理のスタイル」「他館との差別化」といった独善ともいえる形態を引きずってきた。消費者が旅館施設に憧れと満足を得ていた時代は、それでも成り立ってきたが、現在はそれが変化してきた。
その1つの表れともいえるのが、最近の傾向として注目される「地産地消」だ。これは、従来の「その土地独特の料理」を求める意識と同根であるのと同時に、ロハスやスローフードといったマス生産マス消費の対極的な色調も帯びている。ロハスが「健康と持続可能なライフスタイル」であることは改めて述べるまでもないが、これを地域固有の伝統的食材や料理に結びつけることができるだろう。
そこで、地域が一体となって顕在化される温泉地力を考えるとき、第一次産業の生産物=地域固有の食材を、域外の消費者に提供するステージは、まさに旅館にほかならない。それこそが消費者の求める地産地消だ。旅館は、これまでも地域の伝統料理をメニューに加える努力をしてきた。だが、多くの場合それらの料理は、地域色よりも旅館色が全面に出ていたようだ。同一の地域を旅行した消費者が、同じ郷土料理の話をしても、宿泊した旅館が異なれば料理に対するイメージも異質なものになっている。そこに郷土色と旅館色の違いが表れている。
若干横道に逸れるが、ある旅館で「第2厨房」の発想(下図)がなされている。その旅館は、域内で複数の施設を運営しており、第2厨房は各館の「一次処理場」と位置づけている。従来は、それぞれの施設に数人の板前を配置していたが、一次処理を一本化することで板前の数は半減する。厨房作業の人件費が3分の1程度に軽減されるわけだ。もちろん、第二厨房から各館にデリバリーされたものは、それぞれの施設の価格帯に見合った形で二次処理されるために、最終的に提供される料理は従来と遜色がない。だが、経費が削減されてGOPアップに大きく貢献する。
この一例は、地域全体の一次加工を一本化する方向性を示唆している。もちろん、そうした発想が過去になかったわけではないが、確実に成功といえるケースはない。一次加工と二次加工の線引きが不明瞭であったことや、各館が差別化の名の下でこだわり続けたなど種々の要因がある。
前述の郷土色と旅館色の違いは、一次加工を地域一体化することで大幅に解消できるはずだ。それは、ある種の棲み分けにもつながる。ただ、従前の共同厨房的発想のように頓挫させないためには、域内の旅館が一定の基準を明確に定める必要がある。価格の標準ガイドラインやユニフォームシステム(当社GOP名人)など、経営実態を共通のレベルで認識し合うシステムが不可欠だ。
|