|
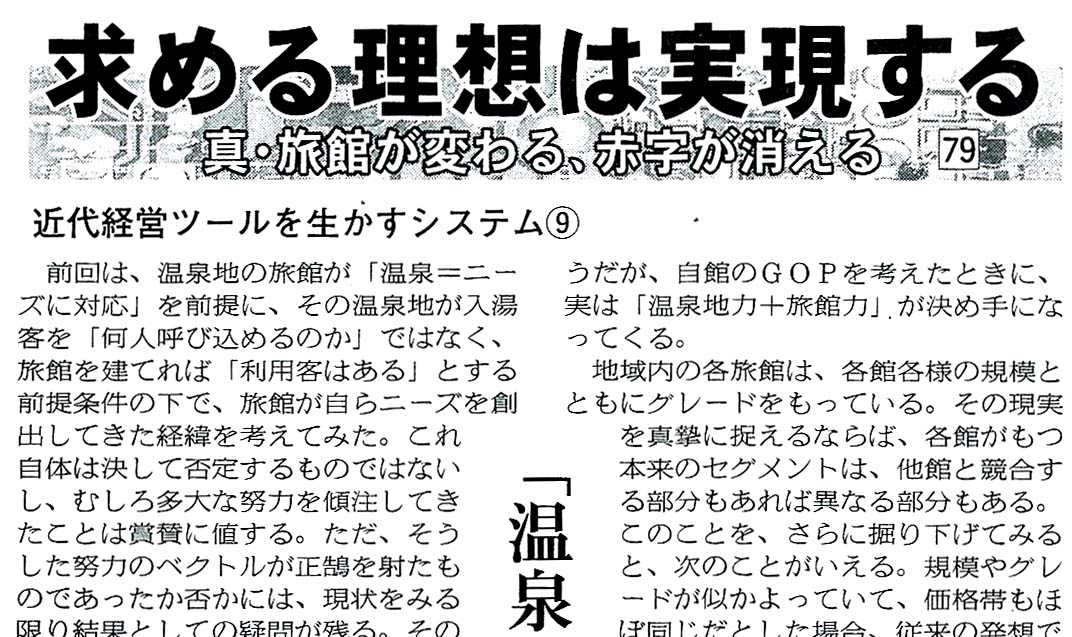 前回は、温泉地の旅館が「温泉=ニーズに対応」を前提に、その温泉地が入湯客を「何人呼び込めるのか」ではなく、旅館を建てれば「利用客はある」とする前提条件の下で、旅館が自らニーズを創出してきた経緯を考えてみた。これ自体は決して否定するものではないし、むしろ多大な努力を傾注してきたことは賞賛に値する。ただ、そうした努力のベクトルが正鵠を射たものであったか否かには、現状をみる限り結果としての疑問が残る。その一つとして今回は、ニーズの前提になっている温泉と旅館とのかかわりを考えることにする。
前回は、温泉地の旅館が「温泉=ニーズに対応」を前提に、その温泉地が入湯客を「何人呼び込めるのか」ではなく、旅館を建てれば「利用客はある」とする前提条件の下で、旅館が自らニーズを創出してきた経緯を考えてみた。これ自体は決して否定するものではないし、むしろ多大な努力を傾注してきたことは賞賛に値する。ただ、そうした努力のベクトルが正鵠を射たものであったか否かには、現状をみる限り結果としての疑問が残る。その一つとして今回は、ニーズの前提になっている温泉と旅館とのかかわりを考えることにする。
今日では、温泉地と旅館名が「○○温泉の△△館」というように、利用者の間ではユニットで認識されているケースが多い。さらに、「○○温泉」が消えて「△△館」という旅館のブランド力で通るケースも少なくない。また、江戸時代の温泉番付に名を連ねているような温泉地は、それ自体のブランド力もあるが、そうでない場合は「△△館」のある「○○温泉」といった具合に、旅館のブランド力が温泉地の訴求を牽引しているケースもある。つまり、歴史的に由緒があって「開湯○○○年」や「△△ゆかりの温泉」と訴求しても、それが誘客に直結するか(ニーズを創出できているか)といえば、どうも心もとない。というよりも、そうした訴求フレーズは、マーケットへのインパクトに欠ける。その結果として、旅館のハードやソフトが吸引力の決め手にならざるを得ないし、現実にそうした展開で経営を続けることができた。その意味では、前段で記したようにニーズを創出していたことになる。
ところが、そうした展開では、施設のリニューアルやイノベーションといった資金の投入を絶えず繰り返す必要があり、GOPアップを阻害する経営ジレンマがつきまとっていた。極論すれば、それを止めたときは、衰退から廃業への道が待っていた。
したがって、その温泉地が入湯客を「何人呼び込めるのか」ではなく、旅館が利用客を「何人集客できるか」に尽きるようだが、自館のGOPを考えたときに、実は「温泉地力+旅館力」が決め手になってくる。
地域内の各旅館は、各館各様の規模とともにグレードをもっている。その現実を真摯に捉えるならば、各館がもつ本来のセグメントは、他館と競合する部分もあれば異なる部分もある。このことを、さらに掘り下げてみると、次のことがいえる。規模やグレードが似かよっていて、価格帯もほぼ同じだとした場合、従来の発想ではいわゆる「競合」と短絡的に結論づけてしまう。逆に、地域の1番店や2番店が突出していると、それ以下の旅館は自ら「十羽一からげ」の諦観をもってしまい、本来なさねばならないセグメントを放棄してしまう。そうした現実を販売(集客)面で多少乱暴にいえば、上位館から埋まった「おこぼれ」が自館のセグメントと思い込むようなケースさえ皆無ではない。これでは、地域としての一体感が生まれない。地域という共通の前提条件の中で「同床異夢」に耽っているのに等しい。
そうした状況を打破するために筆者は、温泉地内の旅館が一体化した販促活動や、さらに進んで棲み分けによる協業化などを提案すると、総論では大方が賛成なのだが、各論に入ると話は一気に頓挫してしまう。こうしたケースは、実に枚挙に暇がないほどだ。いわば、地域というスタンスに立つと「呉越同舟」の実態をさらけ出し、それぞれの異なる思惑が激突して先へ進めなくなってしまう。
だが、自館のシーズを見極めてセグメントを図るならば、まさに前向きな発想が生まれてくる。例えば、同じような規模やグレードであって、しかも価格帯が同クラスだとしても、異なるセグメントは可能だ。なぜなら旅館は、ハードだけでなく料理や接遇などのソフト面に最終的な評価となるからだ。消費者が利用を決定する要因は、そこにある。呉越同舟で成り行き任せよりは、同床異夢でも力を合わせて難関を乗り切ることが、ときには必要だろう。
|

