|
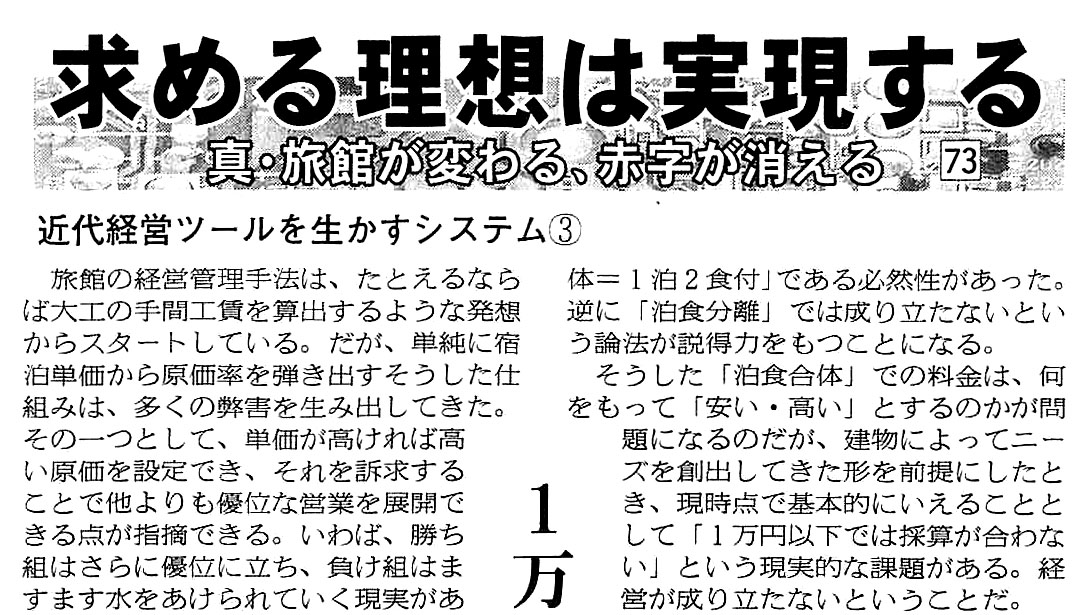 旅館の経営管理手法は、たとえるならば大工の手間工賃を算出するような発想からスタートしている。だが、単純に宿泊単価から原価率を弾き出すそうした仕組みは、多くの弊害を生み出してきた。その一つとして、単価が高ければ高い原価を設定でき、それを訴求することで他よりも優位な営業を展開できる点が指摘できる。いわば、勝ち組はさらに優位に立ち負け組みはますます水をあけられていく現実がある。これは、旅館だけでなく、温泉地や観光地そのものにもあてはめることができる。 旅館の経営管理手法は、たとえるならば大工の手間工賃を算出するような発想からスタートしている。だが、単純に宿泊単価から原価率を弾き出すそうした仕組みは、多くの弊害を生み出してきた。その一つとして、単価が高ければ高い原価を設定でき、それを訴求することで他よりも優位な営業を展開できる点が指摘できる。いわば、勝ち組はさらに優位に立ち負け組みはますます水をあけられていく現実がある。これは、旅館だけでなく、温泉地や観光地そのものにもあてはめることができる。
つまり、手間工賃的な発想による経営管理手法は、旅館商品の魅力を左右することになる。原価率が高ければ「いい商品」になるのは当然だが、それができなければ淘汰されてしまう。市場原理といえばそれまでだが、果たしてそれが旅館業の「業」として正常な姿かどうかは議論の分かれるところだ。
このことは、泊食分離の考え方にもつながっている。ある経営者は「泊食を分離してしまうと旅館業として成り立たない」と言い切った。確かに、温泉地の旅館に宿泊して食事がなければ、宿泊客は困惑する。市中のホテルならば外食は可能だが、温泉地では難しい場合の方が多い。これは、言い古されてきた論法だが、消費者も9割以上がそれを納得しているというデータもある。いわば、旅館は料理を「コマセ」にして集客してきた実績があり、それがホテルとの違いの一つにもなっている。
その背景としては、都市のホテルは宿泊のニーズがあってスタートしているの対して、旅館はニーズの有無ではなく「まず建設」といった形が多い点をあげられる。いわば、建物を建てることでニーズを創出してきた。それが成り立つためには、温泉が誘客資源として大きな役割を果たしていた。それゆえに「泊食合体=1泊2食付」である必然性があった。逆に「泊食分離」では成り立たないと言う論法が説得力をもつことになる。
そうした「泊食合体」での料金は、何をもって「安い・高い」とするのかが問題になるのだが、建物によってニーズを創出してきた形を前提にしたとき、現時点で基本的にいえることとして「1万円以下では採算が合わない」という現実的な課題がある。経営が成り立たないということだ。
例えば、6000円のビジネスホテルに泊まって、何千円かの外食をすれば、トータルで1万円はいってしまう。だが、利用客は6000円に割安感を抱き、それに比べると旅館の1万円超は、2食付や泊まった客室の広さも度外視して高いと感じる矛盾に気づいていない。なぜ、消費者がそうした感覚になるのかは大きな問題だが、その検討は別の機会に譲る。
例えば、ビジネスホテルは6000円で不動産業として成り立っているのに対して、旅館は不動産業として客室単価が確保されていないことに着目してほしい。もちろん、小規模で家族や若干のパートで運営している旅館では、不動産業として4000円、料飲業で3000円の合計7000円も可能だか、ここでは観光地や温泉地で主流となっている一定規模を想定して話を進めたい。
そうなると、経営管理手法の前段として、適正価格とは何かを考えておく必要がある。いわば旅館版ユニフォームシステムの前に、料金設定の「標準ガイドライン」が求められるわけだが、現実ではこの辺りがかなり曖昧になっていることが否めない。
|


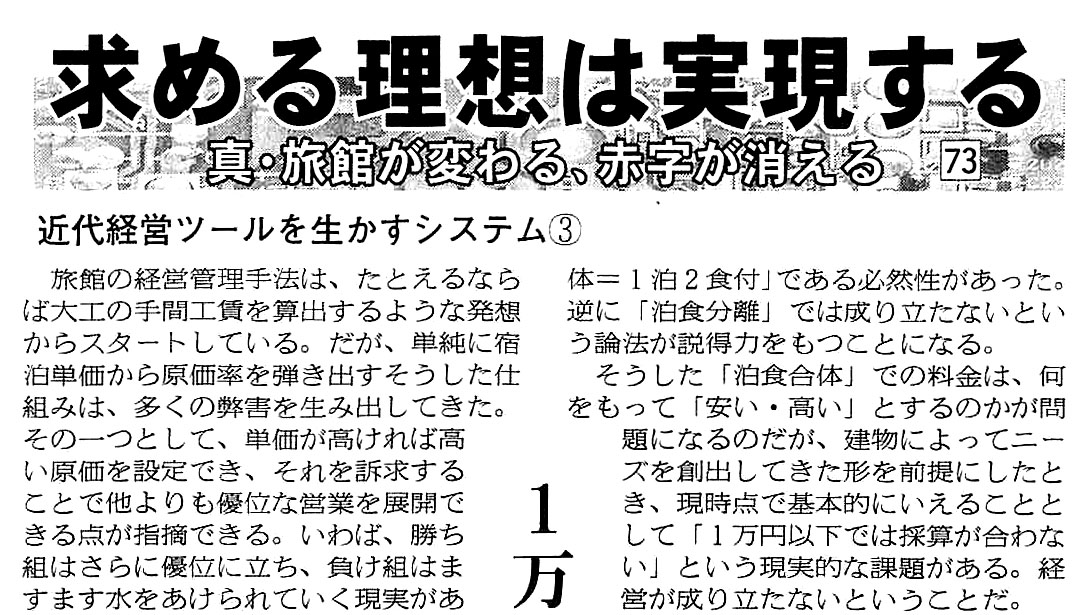 旅館の経営管理手法は、たとえるならば大工の手間工賃を算出するような発想からスタートしている。だが、単純に宿泊単価から原価率を弾き出すそうした仕組みは、多くの弊害を生み出してきた。その一つとして、単価が高ければ高い原価を設定でき、それを訴求することで他よりも優位な営業を展開できる点が指摘できる。いわば、勝ち組はさらに優位に立ち負け組みはますます水をあけられていく現実がある。これは、旅館だけでなく、温泉地や観光地そのものにもあてはめることができる。
旅館の経営管理手法は、たとえるならば大工の手間工賃を算出するような発想からスタートしている。だが、単純に宿泊単価から原価率を弾き出すそうした仕組みは、多くの弊害を生み出してきた。その一つとして、単価が高ければ高い原価を設定でき、それを訴求することで他よりも優位な営業を展開できる点が指摘できる。いわば、勝ち組はさらに優位に立ち負け組みはますます水をあけられていく現実がある。これは、旅館だけでなく、温泉地や観光地そのものにもあてはめることができる。