|
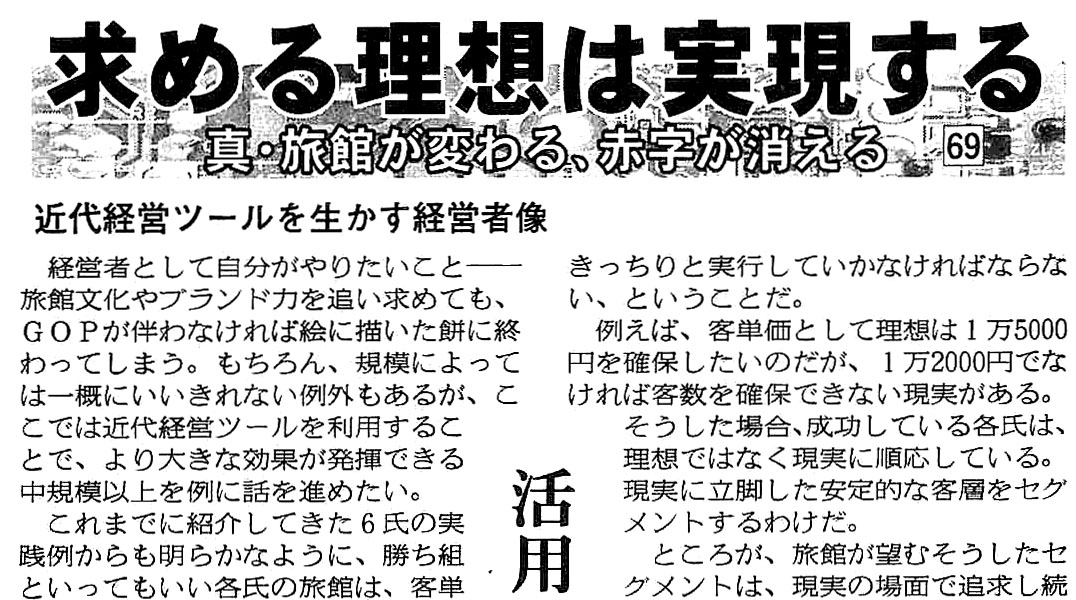 経営者として自分がやりたいこと――旅館文化やブランド力を追い求めても、GOPが伴わなければ絵に描いた餅に終わってしまう。もちろん、規模によっては一概にいいきれない例外もあるが、ここでは近代経営ツールを利用することで、より大きな効果が発揮できる中規模以上を例に話を進めたい。 経営者として自分がやりたいこと――旅館文化やブランド力を追い求めても、GOPが伴わなければ絵に描いた餅に終わってしまう。もちろん、規模によっては一概にいいきれない例外もあるが、ここでは近代経営ツールを利用することで、より大きな効果が発揮できる中規模以上を例に話を進めたい。
これまでに紹介してきた6氏の実践例からも明らかなように、勝ち組といってもいい各氏の旅館は、客単価がずば抜けて高いわけではない。市場のニーズを考えてみると、現在の客単価は1万円から1万5000円ぐらいが妥当といわれている。客層をセグメントするときに、市場のニーズに絞り込んでいるのも各館の共通項の1つだ。そうした基本設定の上で、総消費単価の上積みを図るケースもあれば、単価設定をより高められる別棟をプラスさせて「旅館として自分がやりたいこと」を実現させているケースなどさまざまだ。
さて、「やりたいこと」と「経営」の係わりを整理するために、しばしば例示する私流の喩えを改めて記しておきたい。
それは、旅館の経営者像には、経営に携わる自分自身と旅館の係わり方で、2つの分岐点があるということ。経営路線ともいえるそこでは、「旅館をする」のか「旅館を経営する」のかが最初の分岐点だ。小規模で自分が思い描いた旅館を営むのが前者であり、後者には「自分の仕事として」なのか「企業として」なのかという2つ目の分岐点がある。「企業として」という捉え方以外の2つは、いわゆる家業的な路線といえる。
経営路線として「旅館をする」という願望は、大半の旅館経営者に共通している。それは、旅館文化を顕現することにほかならない。ところが、どんなに好きなことであっても、そこから収入を得られなければ仕事とはいえない。趣味では食べて行けないのと同じだ。また、家業であっても企業であっても、そこから利益を上げて経営を持続させるのが大命題であることに変りはない。自分の「やりたいこと」を気持ちの中で強くもちながら、食べるための「1+1」の計算をきっちりと実行していかなければならな、ということだ。
例えば、客単価として理想は1万5000円を確保したいのだが、1万2000円でなければ客数を確保できない現実がある。そうした場合、成功している各氏は、理想ではなく現実に順応している。現実に立脚した安定的な客層をセグメントするわけだ。
ところが、旅館が望むそうしたセグメントは、現実の場面で追求し続けるのが難しい。その大きな要因として旅行業者とのからみがある。
ある旅館経営者は、大手旅行業者の課長を評して「不良課長」といった。その背景には、自社企画を販売した際に、大手旅行業者の企画商品と異なる価格を設定したところ、その課長が「なぜ、こんな価格で売ったのだ。もう、ウチと提携する気はないのだな」と恫喝されたためだ。その旅館経営者の話からみえてくる旅行業者との接し方は、いうならば「柳の枝」のように、枝葉部分は旅行業者の風に任せて揺れ動くが、幹だけは動じない姿勢を貫いている。風に耐えられない葉が散り、枝が折れることがあっても、経営の根幹部分が折れないように根を張り続けていれば、やがて新しい枝が芽吹き葉も繁ってくるというわけだ。GOPを崩し、経営の根幹部分を揺さぶるような要求に対しては、断固として応じない姿勢を示した。
結果として対象となった葉は失ったが、その旅行業者とのかかわりを絶ったのではなく新しい芽も生まれている。旅館と旅行業者との関係は、「これからも切れることはない」と、その経営者はいった。ただし、旅行業者の意のままに関係を保つのではなく、互いに利する関係でなければならないともいう。また、そうした関係は、企業である旅行業者に対して旅館も「企業」としての姿勢で対応する姿でもあった。こうした経営は、日和見ではなく長期展望によって成り立つものであり、その根底にはGOPに対する強烈なまでの意識がみてとれる。
|


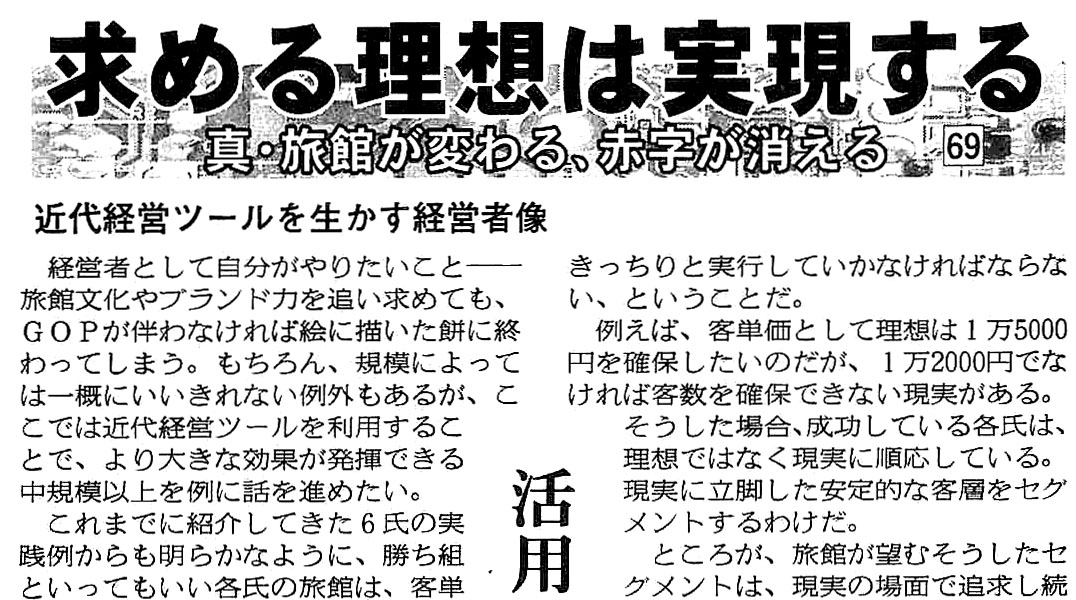 経営者として自分がやりたいこと――旅館文化やブランド力を追い求めても、GOPが伴わなければ絵に描いた餅に終わってしまう。もちろん、規模によっては一概にいいきれない例外もあるが、ここでは近代経営ツールを利用することで、より大きな効果が発揮できる中規模以上を例に話を進めたい。
経営者として自分がやりたいこと――旅館文化やブランド力を追い求めても、GOPが伴わなければ絵に描いた餅に終わってしまう。もちろん、規模によっては一概にいいきれない例外もあるが、ここでは近代経営ツールを利用することで、より大きな効果が発揮できる中規模以上を例に話を進めたい。