|
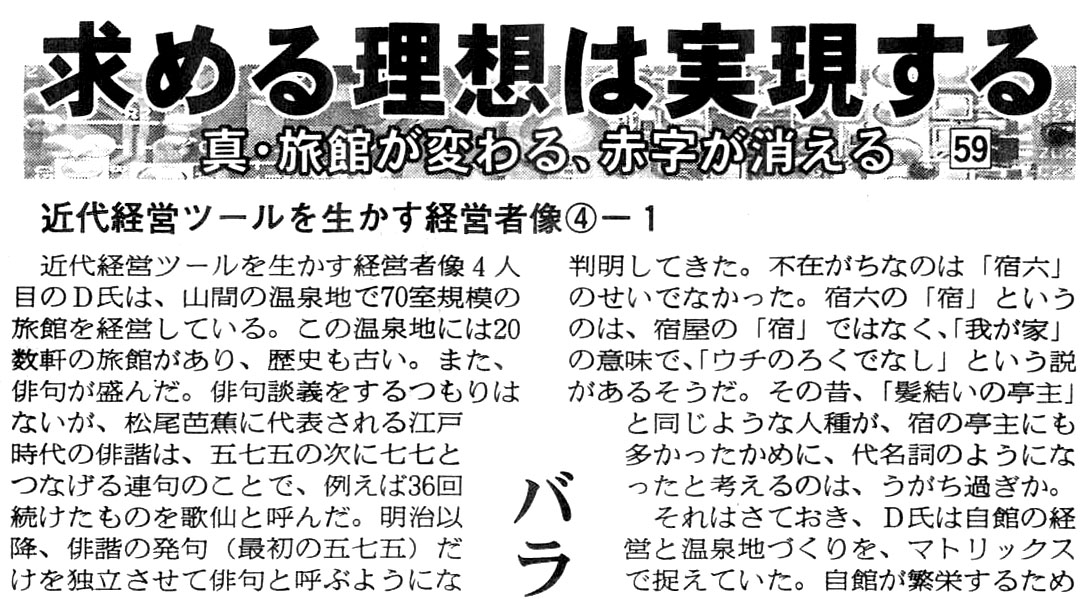 近代経営ツールを生かす経営者像4人目のD氏は、山間の温泉地で70室規模の旅館を経営している。この温泉地には20数軒の旅館があり、歴史も古い。 近代経営ツールを生かす経営者像4人目のD氏は、山間の温泉地で70室規模の旅館を経営している。この温泉地には20数軒の旅館があり、歴史も古い。
また俳句が盛んだ。俳句談義をするつもりはないが、松尾芭蕉に代表される江戸時代の俳諧は、五七五の次に七七とつなげる連句のことで、例えば36回続けたものを歌仙と呼んだ。明治以降、俳諧の発句(最初の五七五)だけを独立させて俳句と呼ぶようになったという。連句は何人もが集まって1作品をつくるために、芭蕉が全国を行脚できた要因の1つにもなっている。行く先々で俳諧の座を開くにはスポンサー役が必要であり、その座元を旅館の主人が務めることも少なくなかった。家業よりも俳諧にうつつを抜かす主人は、文化人なのだが傍目には道楽者に映ったようだ。D氏は道楽者でないが、家業と同じぐらい地域や組合の世話人として忙しく飛び回っているその意味で「土地柄なのかな」と初見のときに、ふと思った。
◇ ◇ ◇
それは、D氏のもとを初めて訪ねたときのことだ。
「いやぁ、何かと忙しくて……」
と、弁解とも牽制ともとれるあいさつをされた。確かに、アポイントを取りつけるまでが一苦労だった。電話をしても不在がちで、しかも行先が不明のこともある。もっとも、こうした旅館経営者は多い。私は、内心で「この旅館もか……」と思った。だが、手許のデータをみると、決して悪いものではない。そこに潜む「何か」が私の興味をそそった。
そして、言葉を交すにつれて理由が判明してきた。不在がちなのは「宿六」のせいでなかった。宿六の「宿」というのは、宿屋の「宿」ではなく、「我が家」の意味で、「ウチのろくでなし」という説があるそうだ。その昔、「髪結いの亭主」と同じような人種が、宿の亭主にも多かったかめに、代名詞のようになったと考えるのは、うがち過ぎか。
それはさておき、D氏は自館の経営と温泉地づくりを、マトリックスで捉えていた。自館が繁栄するためには、地域の旅館や関連業者が力を合わせて「温泉地としての魅力づけを図らなければいけない」というのがD氏の発想原点だった。そのために、地域づくりの先頭に立っていた。自館の経営状況の方は、規模に照らして妥当な利益を生み出しており、GOP比率も旅館平均を上回る20%近い数字を上げている。もう1つ印象に残ったのは、ひけらかす感じは微塵もなくこういった。
「県内では納税額の上位100位ぐらいに入るかな」と。
私は、D氏に好感を抱いた。経営者としても、あるいは人間としてバランスのとれた感覚の持ち主だった。
表現の妥当性は別にして、誘客要因が幾つかある中で、「○○温泉へ行きたい」「○○旅館に泊りたい」という2つのブランド因子が大きいといわれている。ところが、こうした温泉地や旅館は限られている。マニアックな温泉ファンを除けば、ブランド化されていない小さな温泉地や旅館は、消費者が旅行先を選ぶ第1段階の選択肢から外される公算が大きい。D氏が立地する温泉地のように、地元か近県エリアぐらいにしか知られておらず、傑出した旅館による吸引力もない条件下では、そこに立地する旅館が「力を合わせて総力で温泉地名をアピールする」という発想は、まさに正鵠を射たものだ。
私は、旅館の構造改革に必要な近代経営ツールのほかに、温泉地経営の「OSシステム」もツールとして持ち合わせている。さて、何を第1にプレゼンテーションすべきなのか。多少のとまどいがある中で、個としての旅館の構造改革を提案することにした。
|

