|
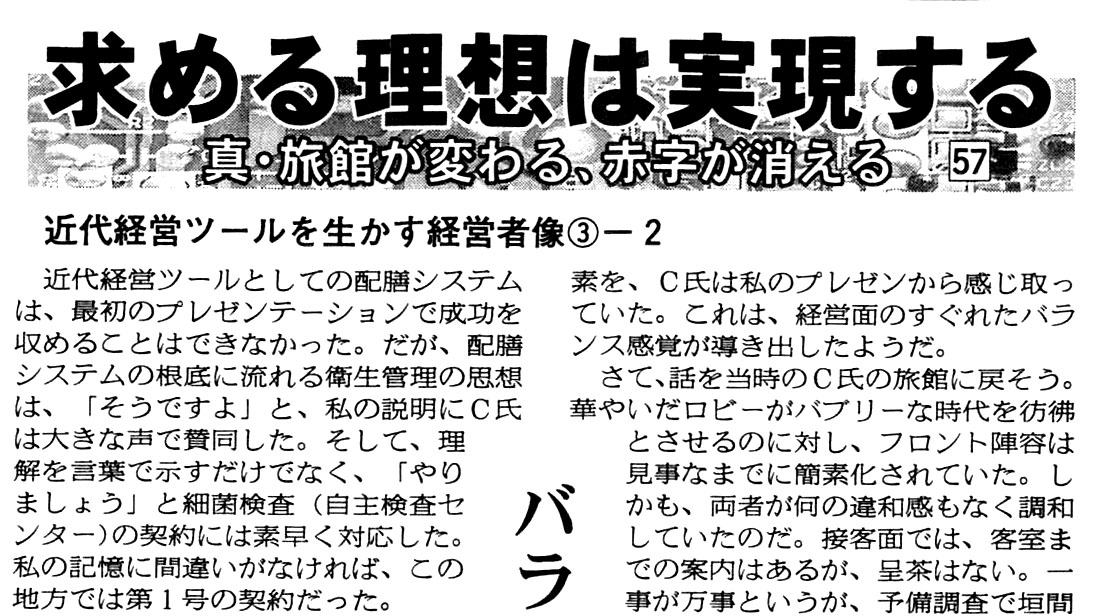 近代経営ツールとしての配膳システムは、最初のプレゼンテーションで成功を収めることはできなかった。だが、配膳システムの根底に流れる衛生管理の思想は「そうですよ」と、私の説明にC氏は大きな声で賛同した。そして、理解を言葉で示すだけでなく、「やりましょう」と細菌検査(自主検査センター)の契約には素早く対応した。私の記憶に間違いがなければ、この地方では第1号の契約だった。 近代経営ツールとしての配膳システムは、最初のプレゼンテーションで成功を収めることはできなかった。だが、配膳システムの根底に流れる衛生管理の思想は「そうですよ」と、私の説明にC氏は大きな声で賛同した。そして、理解を言葉で示すだけでなく、「やりましょう」と細菌検査(自主検査センター)の契約には素早く対応した。私の記憶に間違いがなければ、この地方では第1号の契約だった。
多くの経営者は、営業や経理の状態を程度の差はあっても把握している。そうした中で自社の力量を認知できていない部分があるとすれば、食中毒につながる衛生管理の状態といえる。いわば、ブラックボックスといってもいい。社内にブラックボックスが存在することは、普通に考えれば不安要因になる。
「食中毒は怖い」
大半の旅館経営者は、そう口をそろえていう。だが、実際の予防策を講じる段になると「費用対効果がわからない」といって現状に手をこまぬいてしまう。いわば、表面的な経営効率の話にすりかえてしまうのだ。これに対してC氏は、本質的な経営効率を捉えてすぐさま実行に移した。
私のプレゼンに対して、待ったなしで取り組むべき細菌検査は即座に具体化させたが、相応のイニシャルコストが必要な配膳システムは、大幅な運営変更に現場スタッフが対処できるか否かを見定めてから断を下す姿勢を示した。確かに、配膳システムにはトータルな意味でのコスト削減効果がある。だが、その効果を最大限に引き出すには、現場スタッフの意識改革が欠かせない。なぜなら、計算されたシステムの下で行われる作業は、一定の法則性に準拠することで計算どおりの成果を発揮する。逆に、法則性を無視した作業が行われれば、得られる成果は目減りしてしまう。
また、本質的な面で費用対効果を把握するには、現場スタッフの力量を改めて把握する必要がある。例えば、意識改革の可能性や所用期間など、さまざまな観点から推し測ることになる。それらの要素を、C氏は私のプレゼンから感じ取っていた。これは、経営面のすぐれたバランス感覚が導き出したようだ。
さて、話しを当時のC氏の旅館に戻そう。華やいだロビーがバブリーな時代を彷彿とさせるのに対し、フロント陣容は見事なまでに簡素化されていた。しかも、両者が何の違和感もなく調和していたのだ。接客面では、客室までの案内はあるが、呈茶はない。一事が万事というが、予備調査で垣間見たオペレーションは、配膳システムのシフト運営やオールラウンド的な人員起用で、一般的な旅館に比べると高度なマネジメントを展開していた。
一言でいえば「割り切り」に徹している。それが「ライトな雰囲気で、相応のグレードを漂わせている」といったフレーズとして、当時の私的なメモに残っている。また、華やぎと簡素化の妙を指摘したとき、C氏は即座に断言した。
「うちは、そうした方向には走らない」と。
「そうした方向」とは、いわゆる高額旅館だった。価格面では一定の上限を自ら設けることで、高額旅館を象徴する濃厚な接客サービスを排除していたわけだ。こうした経営スタンスが、バブル期からその後の価格破壊期を通して、業界の常識と異なる一貫した安定経営を実現させていた。これも、バランスのとれた経営感覚の「なせる業」ともいうべきものだった。
そうした中で、細菌検査がスタートした。だが、実際に検査をしてみると意外なことが判明した。ある時の会議でC氏は、調理関係の幹部に対していった。
「なんだ、この検査数値は」と。
かつての苦い経験からC氏は、独自の衛生管理マニュアルで、社内の衛生意識を高めていた。だが、それだけで万全ではないことを、検査数値が示していたのだ。一層の徹底を指示したのだが、目に見えない始末の悪い敵に対しては、やはり限界があった。あってはならない嫌疑をかけられてしまったのだ。
|

