|
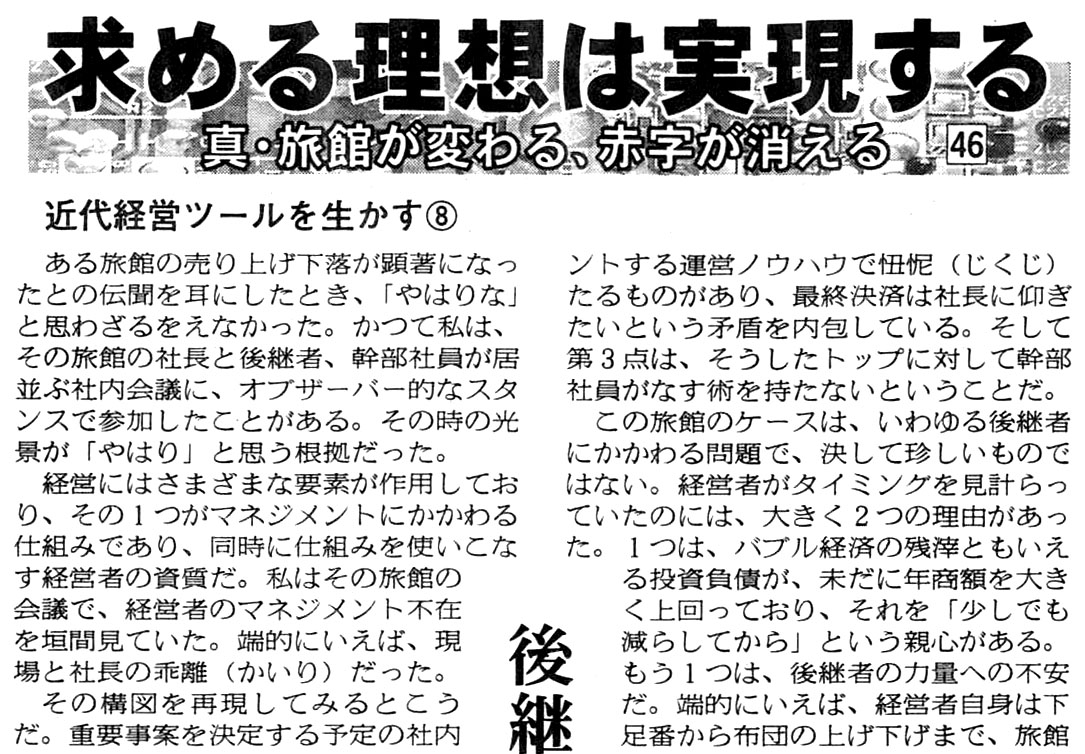 ある旅館の売上下落が顕著になったとの伝聞を耳にしたとき「やはりな」と思わざるをえなかった
ある旅館の売上下落が顕著になったとの伝聞を耳にしたとき「やはりな」と思わざるをえなかった
かつて私は、その旅館の社長と後継者、幹部社員が居並ぶ社内会議に、オブザーバー的なスタンスで参加したことがある。その時の光景が「やはり」と思う根拠だった。
経営にはさまざまな要素が作用しており、その1つがマネジメントにかかわる仕組みであり、同時に仕組みを使いこなす経営者の資質だ。私はその旅館の会議で、経営者のマネジメント不在を垣間見ていた。端的にいえば、現場と社長の乖離だった。
その構図を再現してみるとこうだ。重要事案を決定する予定の社内会議では、専務と幹部社員が居並び、社長の登場を待っていた。名だたる温泉地の老舗旅館であり、会議室も伝統を感じさせるものだったが、驚いたのはその会議風景だった。さながら「御前会議」ともいえる雰囲気なのだ。社長への報告はあるが、報告者の意見具申はない。もちろん、社長以外の出席者が、報告内容に質問することもない。そして、ひと通りの報告を聞き終わった社長は、若干の質問を行った上で、専務と十分に検討を重ねるよう指示を下す。いったい何が決まったのかといえば、重要事項は継続審議、現場で判断できると思われる事項は、専務と幹部社員に委ねられただけで、この日に社長が決裁した事項は何もなかった。
すでに提示した「成功する経営者9つの資質」の2番目「組織長に任せているようで、任せていない」を想起してほしい。これは、単に「任せればいい」という意味ではない。「任せるべきもの・自ら携わるべきもの」を見極めた上での対処にほかならない。
上記の旅館では、この点がどうなのか。第1点として社長の「見極め」が問われるところだ。一見すると、後継者の専務に委ねる形になっている。というのも、この時点で社長は、すでに後継者へのバトンタッチのタイミングを見計らっていた。ところが第2点として、一方の専務は、俗にいう「やりたい気持ち」は満々なのだが、老舗旅館のすべてをマネジメントする運営ノウハウで忸怩たるものがあり、最終決済は社長に仰ぎたいという矛盾を内包している。そして第3点は、そうしたトップに対して幹部社員がなす術をもたないということだ。
この旅館のケースは、いわゆる後継者にかかわる問題で、決して珍しいものではない。経営者がタイミングを見計らっていたのには、大きく2つの理由があった。1つは、バブル経済の残滓ともいえる投資負債が、未だに年商額を大きく上回っており、それを「少しでも減らしてから」という親心がある。もう1つは、後継者の力量への不安だ。端的にいえば、経営者自身は下足番から布団の上げ下げまで、旅館の仕事のイロハを体験してきたという自負がある。これに対して後継者は、そうした下働き的な経験がほとんどない。
したがって、会議の席で経営者が「専務と十分に検討を」といった場合、自分は業務内容を体感していたために、現場の社員と意思の疎通を図れた経験が背後にある。だが、それに乏しい後継者は、現場から瑣末なことがらで突き上げられると手も足もでない。悪くいえば、現場の社員は後継者を「分かってない」と軽んじることにもなる。「現場と社長の乖離」と表現した背景には、旅館にありがちなこの構図があったのだ。
これに対して「後継者を他の旅館やホテルで修行させている」と得意に語る経営者も少なくない
もちろん、すべてを否定するつもりはない。だが、「現場長に任せる」場合が闇雲でないのと同様に、後継者の資質も見定めて育成しなければならない。経営に不可欠なマネジメントを叩き込むこと、いわゆる帝王学が後継者に必要だ。徳川家康や秀忠が戦塵にまみれて築き上げた江戸幕府の三代将軍・家光は、居並ぶ大名に対して「余は生まれながらの将軍」といい放った。それは、弓箭でなく帝王学で諸大名を屈服させ、以後磐石の体制を築き上げた一例だろう。このことを現代流にいえば、マネジメントシステムの確立と実践だと私は思う。
|


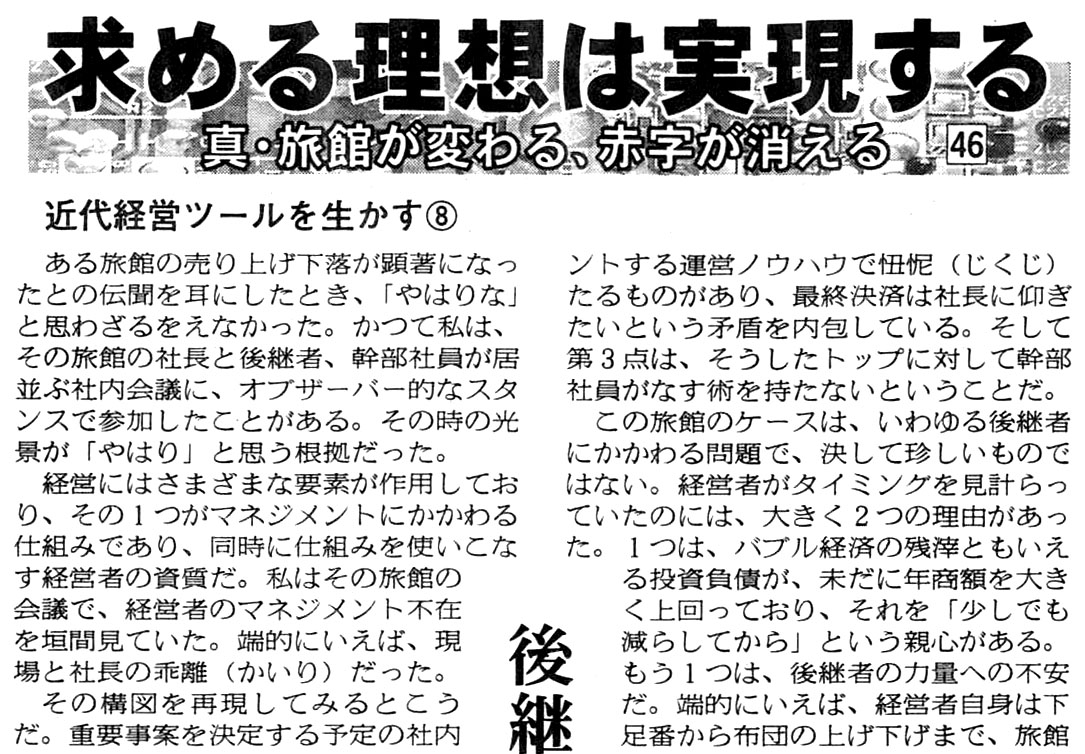 ある旅館の売上下落が顕著になったとの伝聞を耳にしたとき「やはりな」と思わざるをえなかった
ある旅館の売上下落が顕著になったとの伝聞を耳にしたとき「やはりな」と思わざるをえなかった