
|
「儲けるための旅館経営」 その96 |
Press release |
| 2011.9.17観光経済新聞 |
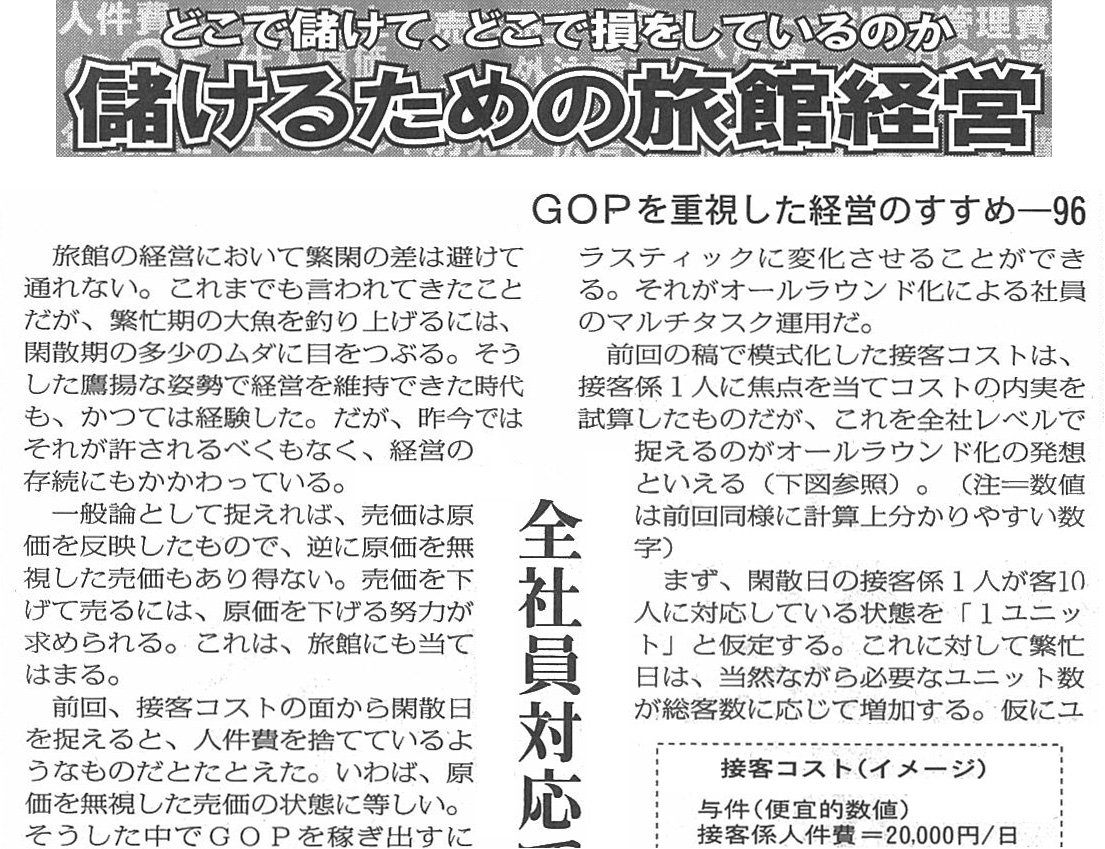 旅館の経営において繁閑の差は避けて通れない。これまでも言われてきたきたことだが、繁忙期の大魚を釣り上げるには、閑散期の多少のムダに目をつぶる。そうした鷹揚な姿勢で経営を維持できた時代も、かつては経験した。だが、昨今ではそれが許されるべくもなく、経営の存続にもかかわっている。 旅館の経営において繁閑の差は避けて通れない。これまでも言われてきたきたことだが、繁忙期の大魚を釣り上げるには、閑散期の多少のムダに目をつぶる。そうした鷹揚な姿勢で経営を維持できた時代も、かつては経験した。だが、昨今ではそれが許されるべくもなく、経営の存続にもかかわっている。
一般論として捉えれば、売価は原価を反映したもので、逆に原価を無視した売価もありあ得ない。売価を下げて売るには、原価を下げる努力が求められる。これは、旅館にも当てはまる。 前回、接客コストの面から閑散日を捉えると、人件費を捨てているようなものだと譬えた。いわば、原価を無視した売価の状態に等しい。そうした中でGOPを稼ぎ出すには、運営コストを圧縮して、原価を下げる以外にないことは分かっている。しかし、コストを下げればクオリティが維持できないジレンマが、常につきまとっているのも現実だ。 なぜならば、旅館は「温泉」(天然や人工を問わず、大浴場や露天風呂など)と「安らぎ」、そして「料理」の3つを売り物にしてきた。言葉を換えれば、施設と接遇が旅館にとっての「観光資源」とも言え、そのどれにも初期投資だけでなく、維持や運営のコストがかかっている。コストの削減は、そうした意味で捉えれば、維持や運営を軽視することになりかねないからだ。 加えて、それらの値打ちが下がれば、売価はさらに下がってGOPが目減りし、次の投資への基礎体力も失せてしまう。単価を下げることで客の歓心や満足は得られるかもしれないが、経営的には満足とほど遠い。しかも、さらなる魅力づけをしていかなければ、客からは簡単に見捨てられる。 これらを並べ立てると八方ふさがりと言える状況だが、筆者としては「コストは下げられる」と断言したい。上記のような堂々巡りの状況は、前回も指摘したタテ割り組織の運営形態が生みだしたものであり、客動線の時系列と整合させた運営システムを構築することで現状はドラスティックに変化させることができる。それがオールラウンド化による社員のマルチタスク運用だ。 前回の稿で模式化した接客コストは、接客係1人に焦点を当てコストの内実を試算したものだが、これを全社レベルで捉えるのがオールラウンド化の発想といえる(下図参照)。(注=数値は前回同様に計算上分かり易い数字) まず、閑散日の接客係1人が客10人に対応している状態を「1ユニット」と仮定する。これに対して繁忙日は、当然ながら必要なユニット数が総客数に応じて増加する。仮にユニット数が2倍になったとしても、繁閑両日の接客コストを比較した場合、どちらも2000円で変わらない。同様に対売上比率も変化しない。これは数字のマジックではない。図中の繁忙日のグレーのユニットが、これまで非接客要員とされてきた社員を、オールラウンドによる接客要員化したものだ。ただし、非接客要員で1ユニットを編成すると言う意味ではない。また、基本となる接客係のユニットを繁閑のどの時点で設定するかは、旅館個々の規模や価格帯ほか現状解析を適切に行い、最も効率的な組み立て方をしなければならない。(つづく) |