
|
「儲けるための旅館経営」 その77 |
Press release |
| 2011.4.16/観光経済新聞 |
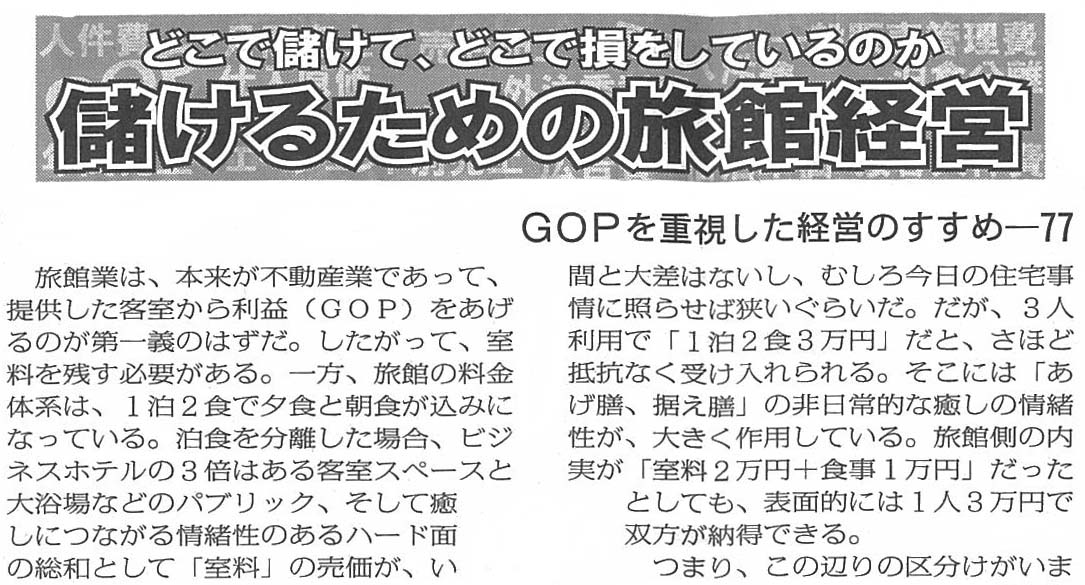
旅館業は、本来が不動産業であって、提供した客室から利益(GOP)をあげるのが第一義のはずだ。したがって、室料を残す必要がある。一方、旅館の料金体系は、1泊2食で夕食と朝食が込みになっている。泊食を分離した場合、ビジネスホテルの3倍はある客室スペースと大浴場などのパブリック、そして癒しにつながる情緒性のあるハード面の総和として「室料」の売価が、いったいいくらになるのか。 前々回の稿で例示したビジネスホテルとの比較を、別の観点から捉えてみよう。ビジネスホテルで就寝単機能の1室5000円の料金を、不動産業を維持していく最低ラインと仮定すれば、スペースが3倍の旅館室料は1万5000円。実勢定員3人の利用を仮定して按分すれば、泊食の「泊」は1人当たり5000円。最近の低価格帯の7000〜8000円だと、夕食と朝食の「食」は2000〜3000円の売価ということになる。 こうした計算方法、そして表示をした場合、客の側からみても旅館側からみても極めて乱暴なものに違いない。とりわけ客側からみると、室料に対する価値評価と現実の金額への整合面で、納得のできない部分がある。それは、宿泊料金に対する消費者の捉え方、あるいは理屈ではないイメージの部分ともいえる。かねて例示したように、海外の高級ホテルが日本に進出できない理由の1つと根底で類似している。端的にいえば、食事のつかない室料だけで1泊5〜6万円クラスのホテルには、大半の日本人が馴染めない。うがった表現をすれば、泊るための客室は「あって当たり前」であり、いわば空気や水、安全といったものに近いニュアンスを抱いている。では、何が「室料(泊)」なのかといえば、冒頭の「癒しにつながる情緒性」の総和といった捉えどころのない部分に帰結する。 極端な例ではあるが「12.5畳+次の間+広縁+露天風呂」の客室占有スペースで、仮に「室料(泊)」だけで6万円を表示すれば、大半の消費者が「高い」と感じる。露天風呂を除けば、日常の住空間と大差はないし、むしろ今日の住宅事情に照らせば狭いぐらいだ。だが、3人利用で「1泊2食3万円」だと、さほど抵抗なく受け入れられる。そこには「あげ膳、据え膳」の非日常的な癒しの情緒性が、大きく作用している。旅館側の内実が「室料2万円+食事1万円」だったとしても、表面的には1人3万円で双方が納得できる。 つまり、この辺りの区分けがいまだに曖昧であり、1泊2食表示から脱却できないでいる。もちろん、それが「間違いだ」という気は毛頭ない。日本の消費者にとっては1泊2食の価格表示は、長い慣習によって根付いたものであり、その歴史を踏まえれば最善のビジネスモデルといっていいのかもしれない。 だが、昨今は例示した3万円の価格が通用する時代ではなくなった。1万5000円だった単価を1万円に引き下げ、さらに7000〜8000円でなければ売れなくなった時代では、改めて旅館側での内実を明確に位置付けて、それに対処する必要がある。そのために筆者は「コストバランス50%」を提唱してきた。この50%のグループに包含されるコストは、人件費、原材料、消耗品と備品補充などだ。もう一方の50%グループは、GOPや返済原資ほか前記以外のコストであり、このグループを不動産業として第一義の室料(泊)でくくっている。その意味では、従来の泊食分離とは発想の根底が違う。 つまり、前者の50%グループは泊食の「食」にかかわるコストをひとまとめにしたもので、いわば「料理運営コスト」と表現できる。ただし、すべての価格帯で「コストバランス50%」が万能なわけではない。下は1万円を割り込んだ辺り、上は2万円を超えた辺りから45%、40%と比率がそれぞれ下がっていく(第44回「3階層運営でコスト50%図る」参照)。
ポイントは、料理コストを見直して、価格グレードに見合った「情緒性の総和」として、満足の与えられるコスト構成を打ち出すことだ。(つづく) |