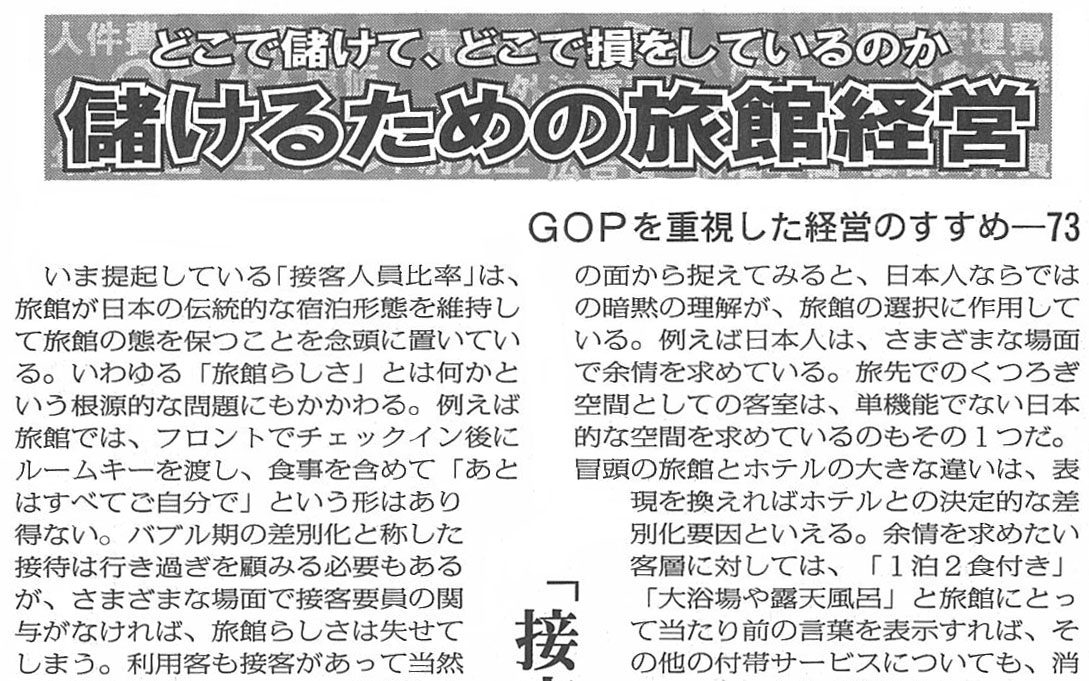|
「儲けるための旅館経営」 その73 |
Press release |
| 2011.3.19/観光経済新聞 |
|
一方、宿泊単価は下がり続けており、今後の上昇には期待があまりもてない。数年前ごろには、団塊世代が定年を迎えたあと余暇活動が活発化するとみなされ、観光宿泊業界でも皮算用を弾いていた。ところが、実際に団塊世代の定年が始まってみると、皮算用は大きく外れた感がある。リーマンショックで世界的に景気が大幅に後退したほか、国内は政局の混乱、最近ではチュニジアの政変が中東だけでなくさらなる広がりをみせ、国内外の世情が混乱している。これらの要件が複合的にからみあい、消費の主流になるはずだった団塊世代の財布のヒモは固く絞られた。宿泊への値ごろ感も1万円以下にシフトしている。 こうした状況下での選択肢は、旅館の伝統的な形態を維持するか、チェックイン後の接客を排除してホテル化するかだ。旅館形態を維持するならば、現時点で抱えている低価格化の大きな問題点を克服しなければならない。逆にホテル化を選択した場合、前回例示した不動産業としての1平米あたり室料で採算が合わない。旅館の客室は、ホテルのようなベッドルームとして単機能化されたものではないために、ハードのイニシャルコストとソフトのランニングコストが、ホテルと比較にならない。 若干横道にそれるが、旅館とホテルを日本人の価値観、あるいは文化への意識の面から捉えてみると、日本人ならではの暗黙の理解が、旅館の選択に作用している。例えば日本人は、さまざまな場面で余情を求めている。旅先でのくつろぎ空間としての客室は、単機能でない日本的な空間を求めているのもその1つだ。冒頭の旅館とホテルの大きな違いは、表現を換えればホテルとの決定的な差別化要因といえる。余情を求めたい客層に対しては、「1泊2食付き」「大浴場や露天風呂」と旅館にとって当たり前の言葉を表示すれば、その他の付帯サービスについても、消費者はおおむね常識として理解してくれる。これは、まぎれもなく旅館であることの優位性であり、ホテルでは詳細な説明を加えなければ、施設についてのイメージをもってもらえない。いい換えれば、永年にわたって培われてきた「日本旅館」のブランド力であり、それを標榜できること自体が旅館の利点にほかならない。商品として、国民の誰もが旅館や温泉と耳にしただけで概要をイメージできるブランド力は、他に換え難いものがある。国民に認定されたブランド力は、今後も活用すべきだと筆者は考える。 本題に戻ろう。選択肢として前述した旅館形態の維持を前提に、低価格化の問題克服(旅館らしさを維持しつつコストの削減)を訴え、社員定数の見直しと具体的な指標として接客人員比率を提唱している。 この接客人員比率を実際の旅館にあてはめると、現状では接客に直接関与する人員が、全社員数の3分の1程度にとどまっている。一方、フロント・ラウンジや事務所のオールラウンド化によって3分1の人員余剰が推定でき、さらに厨房をはじめ間接人員も同じ手法をとれば、合計で3分の2の余剰が出る。極論をいえば、現状の3分の1の社員総数でも運営が可能といえる。 こうした計算をそのまま現実化することは、現状のオペレーションでは非現実的だが、精密なプログラム化によって運営すれば可能だ。何よりも、日本旅館のブランド力が生きてくる。(つづく) |