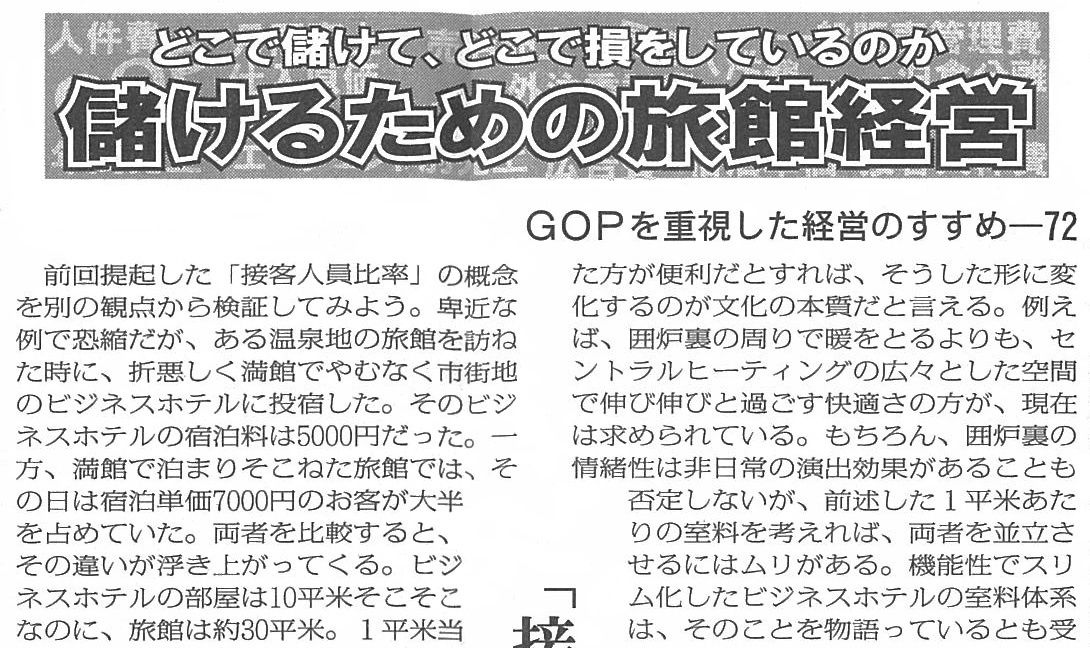|
「儲けるための旅館経営」 その72 |
Press release |
| 2011.3.12/観光経済新聞 |
|
1平米当たりの室料の観点から捉えると、調度やサービスを室料確保の最低限にスリム化したビジネスホテルの1平米500円と、それなりの情緒性やサービスなどを備えた旅館の250円では比較にさえならない。だが、それが低料金の実態でもあるの否定できない。そして、そうした室料のあり方は、残念ながら今後も続くとみられる。 さて、日本旅館の特徴を改めて考えてみると「部屋食」という形がある。これは、日本の文化と言ってもいい。これまでの日本の家屋では、同じ1つの部屋であっても、ちゃぶ台を出せばダイニングやリビングになり、それを片づけて布団を敷けばベッドルームになる多機能性が特徴だった。ところが、最近の日常生活ではそうした部屋の多機能性が失われてきた。生活の各シーンによる部屋の使い分けだ。こうした方が日常生活で使い勝手がいい。旅館の経営的な観点で捉えれば、泊食を分離した機能別空間が求められる。それが、いわゆる今日的な消費者のニーズでもある。 余談だが、文化とは「理想を描いて実現しようとする精神活動」であり、結果としてさまざまな事物や様式が生まれ、それが文明だとされている。つまり、多機能性よりも機能を特化して組み合わせた方が便利だとすれば、そうした形に変化するのが文化の本質だといえる。例えば、囲炉裏の周りで暖をとるよりも、セントラルヒーティングの広々とした空間で伸び伸びと過ごす快適さの方が、現在は求められている。もちろん、囲炉裏の情緒性は非日常の演出効果があることも否定しないが、前述した1平米あたりの室料を考えれば、両者を並立させるにはムリがある。機能性でスリム化したビジネスホテルの室料体系は、そのことを物語っているとも受けとめられる。 また、室料について別の見方もできる。例えば日本は、人口が1億人を超えてGDPも世界に冠たる経済大国であるにもかかわらず、世界的にチェーン展開をしている4星、5星クラスのホテルは、日本での出店率がきわめて低い。そうしたホテルチェーンの狙い目は、室料で400〜600ドルの客層に置かれている。円に換算すれば室料だけで3〜5万円ぐらいになる。出店率の低さは、日本でホテル展開をした場合に、室料がとれないことの裏返しとみていいだろう。これは、日本の文化とも関連する概念の延長線上にあると筆者は考えている。 旅館の「しばり」ではもう1つの大きな要素として1泊2食の「食」があるる。旅館に泊まれば「夕食はついている」のが当たり前と消費者は受けとめている。その意味では、客室提供が基幹事業である不動産業業の旅館は、ホテル形式と比べてスタート時点で料金に50%のハンディを課せられているのに等しい。しかし、それでもGOPを稼ぎ出して経営を成り立たさなければならない。 そこで、運営オペレーションをドラスティックに改編することが生き残りの決め手であり、本稿のテーマでもある。つまり、人的サービスを切り離せない以上、「接客人員比率」を改善していくことがGOP確保に欠かせない。前回、社員総数80人で接客係30数人を例示したが、視点をかえれば、80人を50人に減らす方法もある。(つづく) |