
|
「儲けるための旅館経営」 その138 |
Press release |
| 2012.8.25観光経済新聞 |
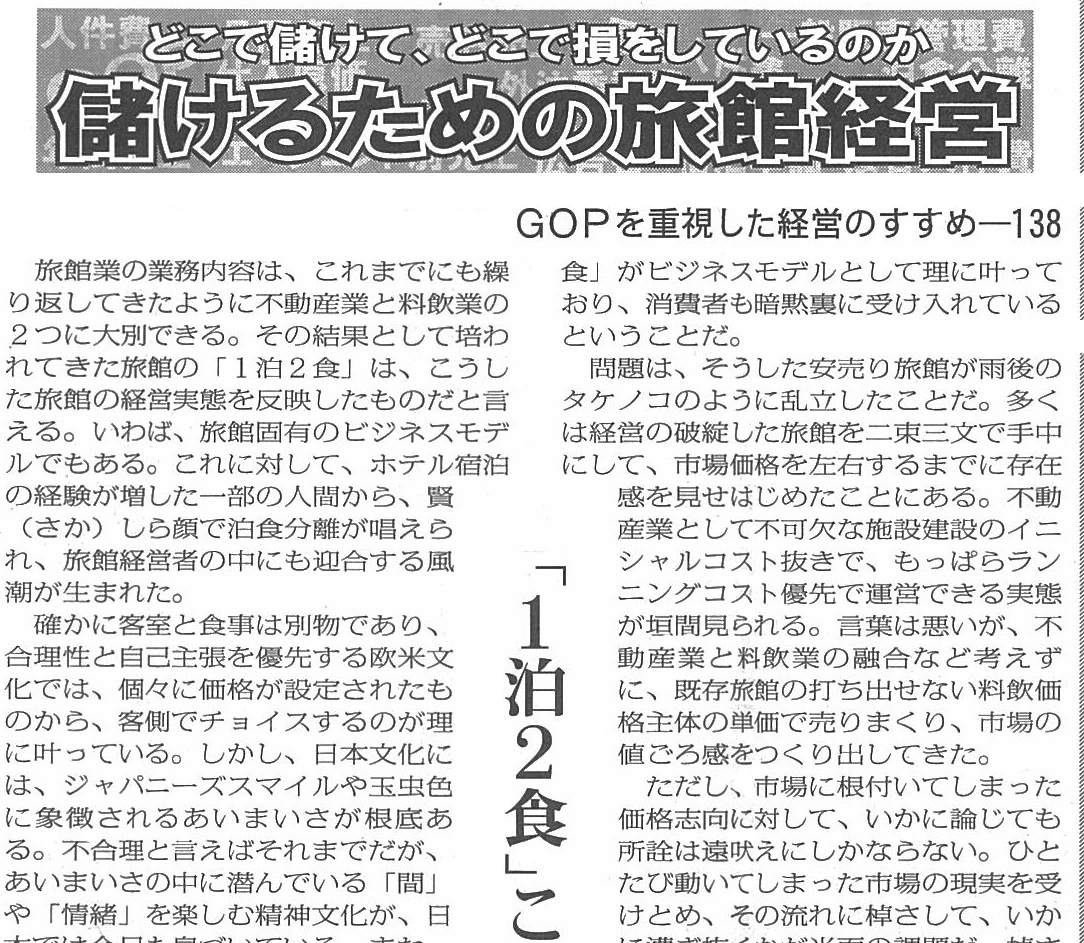
旅館業の業務内容は、これまでにも繰り返してきたように不動産業と料飲業の2つに大別できる。その結果として培われてきた旅館の「1泊2食」は、こうした旅館の経営実態を反映したものだと言える。いわば、旅館固有のビジネスモデルでもある。これに対して、ホテル宿泊の経験が増した一部の人間から、賢(さか)しら顔で泊食分離が唱えられ、旅館経営者の中にも迎合する風潮が生まれた。 確かに客室と食事は別物であり、合理性と自己主張を優先する欧米文化では、個々に価格が設定されたものから、客側でチョイスするのが理に叶っている。しかし、日本文化には、ジャパニーズスマイルや玉虫色に象徴される曖昧さが根底ある。不合理と言えばそれまでだが、曖昧さの中に潜んでいる「間」や「情緒」を楽しむ精神文化が、日本では今日も息づいている。また、そうした日本文化が薄れたと言う人もいるが、宿泊先として旅館を選ぶ客層には、伝統的な旅館の「情緒」や就寝と入浴、そして食事を融合させた宿泊形態が、選択肢の上で大きな位置付けとなっているのも確かだ。そこでは不合理や曖昧さに対する意識は希薄だとみていい。 余談だが、帰宅した夫に「お風呂にしますか、食事にしますか」の日常フレーズは、非日常の旅先でも生きている。とりわけ家庭で迎える側の女性層には、旅館でのそうした選択自体が非日常にほかならない。また、泊食分離に関連して旅館の食事を「お仕着せ」と捉え、選択肢にバラエティを持たせる声もあるが、これも観念論に近い。主婦層が日々の食事づくりで、献立を考えるのにどれだけ腐心していることか。何も考えずに供される食事は、まさに至極の非日常であると、旅館は捉え直す必要もある。 本題に戻ろう。好ましい例とは言い難いのだが、最近の価格志向を象徴する安売り旅館でも、販売面では「1泊2食」の表示が大半を占めている。このことが何を意味しているのか。結論の1つとして言えることは、旅館にとって「1泊2食」がビジネスモデルとして理に叶っており、消費者も暗黙理に受け入れているということだ。 問題は、そうした安売り旅館が雨後のタケノコのように乱立したことだ。多くは経営の破綻した旅館を二束三文で手中にして、市場価格を左右するまでに存在感を見せはじめたことにある。不動産業として不可欠な施設建設のイニシャルコストを抜きで、もっぱらランニングコスト優先で運営できる実態が垣間見られる。言葉は悪いが、不動産産業と料飲業の融合など考えずに、既存旅館の打ち出せない料飲価格主体の単価で売りまくり、市場の値ごろ感をつくり出してきた。 ただし、市場に根付いてしまった価格志向に対して、いかに論じても所詮は遠吠えにしかならない。一たび動いてしまった市場の現実を受けとめ、その流れに棹さして、いかに漕ぎ抜くかが当面の課題だ。棹さすとは流れに抗うことではなく、船をコントロールして流れに乗ることの意味でもある。これも日本人が古来もっていた処世観だ。さすべき棹のヒントは、奇しくも安売り旅館が価格破壊のビジネスモデルとして証明した「1泊2食」にある。いわば、ビジネスとして成り立つための旅館商品は、「泊食分離」ではないと言うことだ。 つまり、安売り旅館が成り立つのは、俗な言い方をすると販売方法としての「1泊2食」は間違っていないということ。ただ、前段で述べたように旅館は、不動産産業と料飲業を融合させた日本の宿泊文化を、トータルで売っている点に注視する必要がある。これは、経営において2つのモデルの必要性を意味している。1つは、消費者が受け入れている「1泊2食」を、外に向けたビジネスモデルとして活用すること。もう1つは、内に向けたマネジメントモデルを各社の実情に合わせて創出し、定着させること。この2本建てが旅館の経営モデルにほかならない。これが経営において「泊食分離」の視点が必要な理由でもある。(つづく) |