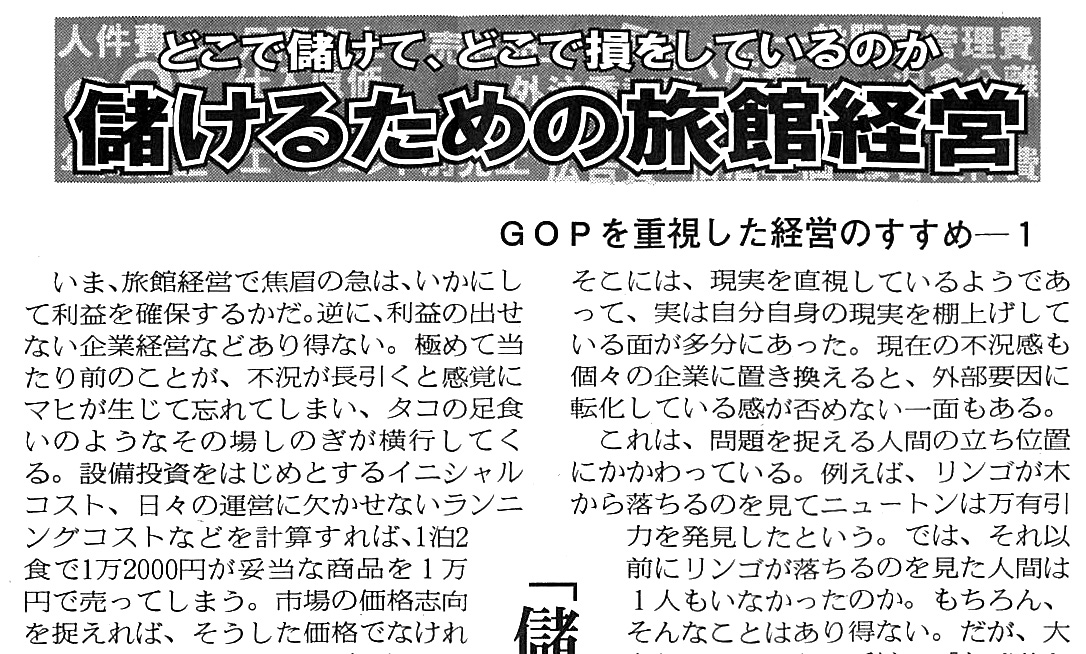|
「儲けるための旅館経営」 その8 |
Press release |
| 2009.9.12/観光経済新聞 |
|
これを旅館業にあてはめると、売上原価の最大項目は、料飲サービス料である調理、料理輸送、接客、食器洗浄など料理に関わるすべての人件費と原材料、消耗品、厨房設備運営費のほか、運営にかかわる一切のコスト(旅行業者への手数料や初期投資の案分額を含む)などだ。 そして、旅館業における儲けも製造業の「売上高-売上原価=売上総利益」の構図と同じで、利用客から受け取る利用料金(売上高)から、売上原価を差し引いた残りにほかならない。つまり、売上原価を抑えれば抑えるほど旅館の儲けは大きくなるわけで、その最大注目項目が料飲サービス料ということになる。 こうした発想は、従来の経理科目の区分とは異なるかもしれない。また、第6回の稿で「旅館の経営は、一般的な経営の概念に当てはまらないケースがいくつもある」と述べたのは、製造業のような在庫の概念がもてないこともその1つといえる。今日の客室が売れなければ、それを明日に持ち越して売ることができない。また、多品種少量生産ではないが、旅館の客室は極端に言えば1室ごとに異なっている。例えば「広さ=平米数」「ロケーション=ビュー効果」「調度品=プライオリティー」などが、極めて多種多様だ。一概に「室料」と言っても、単純に弾き出すことができない。かつて、大雑把に「1畳1000円」などと言った笑うに笑えない話もあった。12.5畳で次の間つきの1畳と、床の間もない6畳の1畳当たりの単価が、同じ換算レートであっていいわけがない。これは極論にしても、判断基準となる指標は業界総意の下で必要だろう。 また、儲けを計る指針なり指標も求められる。とりわけ価格志向が強まるなかで、前述の「売上高-売上原価=売上総利益」の構図と、儲けとの関係を考える必要がある。詳細は別の機会に譲るが、例えばアメリカのホテルでは、客室価格の設定で「ラック・レート」(Rack Rate=一般的な基準価格)、「グループ・レート」(Group Rate=団体割引価格)のほか、大口企業向け、無料提供などがある。これらは、日々の経営状態を把握するための指数化に欠かせないもので、その指数としては、①客室稼働率(Room Occupancy Percentage)②アベレッジ・デイリー・レート(Average Daily Rate)③レバパー(RevPAR=Revenue Per Available Room)などがある。 このうち客室稼働率は日本でも広く使われている。ADR(アベレッジ・デイリー・レート)は1室当たりの平均料金で、基準価格と割引価格の販売の状況などを把握するために使われるが、客室ごとに条件に違う和室では、なじみ難い面もある。3つめのレバパーは、客室稼働率とADRを融合したような指数だが、今回の冒頭で述べた「室料」の管理では大きな意味を持っている。例えば、前回のケーススタディで平均単価が1万5000円だった旅館が、安売りで7000~8000円を受け始めた場合、レバパーを弾き出すことで実勢を把握することが可能であり、室料管理につながる。 いずれの指数もアメリカのホテルのように客室タイプに一定の画一性があれば有効に機能するが、和室主体の旅館では難しい面もある。だが、今後の経営管理手法として検討の必要もある。 |
| (つづく) |