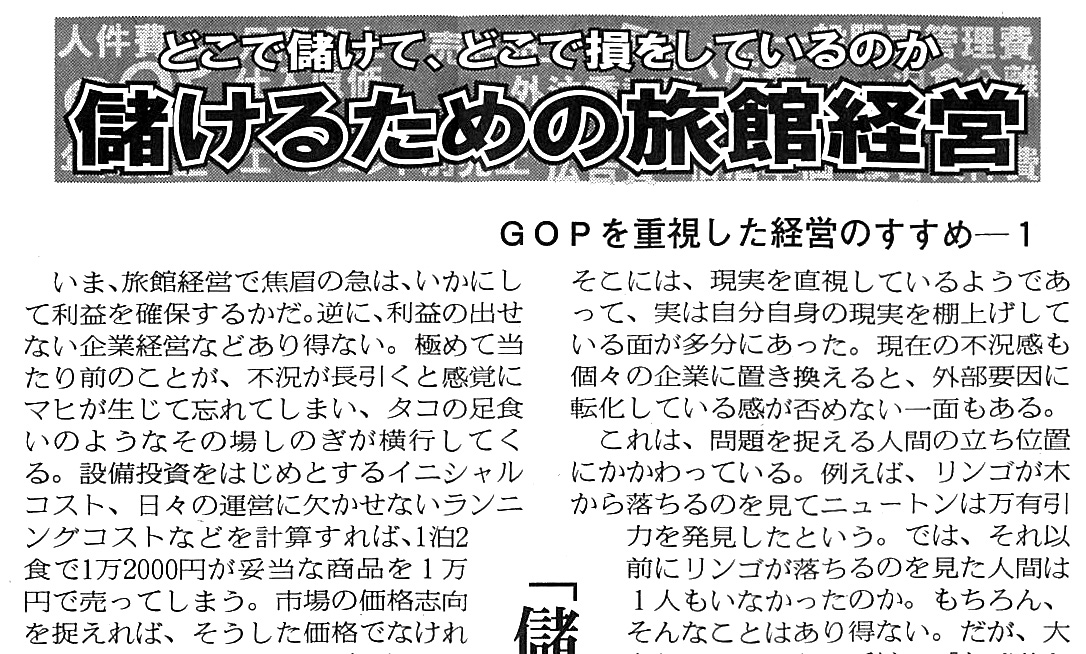|
「儲けるための旅館経営」 その7 |
Press release |
| 2009.9.5/観光経済新聞 |
|
これに関連した話題としてある旅館の事例を紹介してみよう。モデル旅館は、年商25億円ほどの大型旅館で、平均単価の実勢は1万5000円ほどだ。価格志向の強い昨今では「まずまずのレベル」を維持していた。あえて過去形にしたのは、大型団体が急激に減少したことから、8000円台も受けるようになり、さらに最近では7000円台にまで下げてきた。といって低単価政策で客数が大幅に増加したわけではなく、かろうじて維持している程度にとどまっている。従前の年商を単価で割れば年間17万人弱であり、現在の客数を従前の1万5000円台が4割、7000〜8000円台が6割と推定すれば、平均単価の推定値は1万500円で4500円のダウンになる。当然ながら年商も18億円程度にしかならない。 そこで問題となるのが料飲率だ。かつては、地域特性もあって施設の豪華さや温泉のほかに、料理にもかなりのコストをかけていた。料飲サービス料(調理、料理輸送、接客、食器洗浄など料理に関わるすべての人件費、原材料、消耗品、厨房設備運営費など)は、実勢単価の50%近くに達していた。つまり、1万5000円のうち7000円ほどが料飲サービスのコストだった。もちろん、現状の単価7000円台にそれだけのコストをかけられるわけもなく、従前と同程度の料率50%強(3500円台)に落としている。 そこから逆方向の単純な算数をしてみよう。単価1万5000円の時代に7000円の料飲サービス料を費やすと、室料としての残りは8000円弱だった。この室料には料飲サービス以外の人件費(フロント、経理、清掃、その他)、販売費、一般管理費、建物減価償却費、そしてGOPが含まれている。つまり、室料として8000円弱を確保し、年間全体では14億円弱が必要だったのだ。ところが、平均単価が4500円ダウンした現在の年間室料は10億円にしかならない。オーナーが言う。 「さまざまなコスト削減を試みてきたが、あと2億円の削減を図らないと今後の経営を維持できない」と。これが現状なのだ。 さて、冒頭の「宿泊と温泉と食事」の三位一体が、旅館の評価要因であることを改めて考えてみたい。旅館の基本的なファクターとしては、例えば温泉地の旅館は「温泉に入る」という観光資源で客を集めている。そうした中で客単価の高い旅館は、ハードも立派で温泉も満足できる。加えて料理が高質であれば申し分ない。逆に、どれか1つでも不評があれば、評価は一気に下がる。その意味では、確かに三位一体なのだ。 ところが、料理は高価な原材料だけが評価の対象ではない。多少乱暴だが、例えば民宿の料理は、地元素材を大量に出されて満足するケースもあるが、評価はそれに関してのみだ。少量ずつだが洗練された料理の旅館と、どちらが満足度が高いかは観点が違う。そこには、料飲サービス料の操作によってGOPアップの方策が残されていることを示唆している。 前出のオーナーが言った「あと2億円」にしても、単価1万5000円の料飲率を40%、7000円台は30%で賄える工夫をすれば、2億円程度を弾き出すことは難しくない。ハードそのものは1万5000円の単価に絶えるグレードを備えている以上、料飲率を下げても評価全体に与える影響が極端に出るとは考えにくい。この点は、前回のケーススタディでとりあげた単価2〜3万円の旅館とは違う。 肝心なことは、三位一体によって形成された既成概念の評価にとらわれないことだ。だが、料飲率を多少操作しても評価に影響の出にくい「ハードを維持している」という条件がつく。ここが難問だ。バブル崩壊以降の厳しい経営環境から、多くの旅館でGOPが下がり、設備の維持やリニューアルへの再投資が難しくなっている。鶏と卵の議論ではなく、まず料飲率を見直すのが第一歩だ。 |
| (つづく) |