|
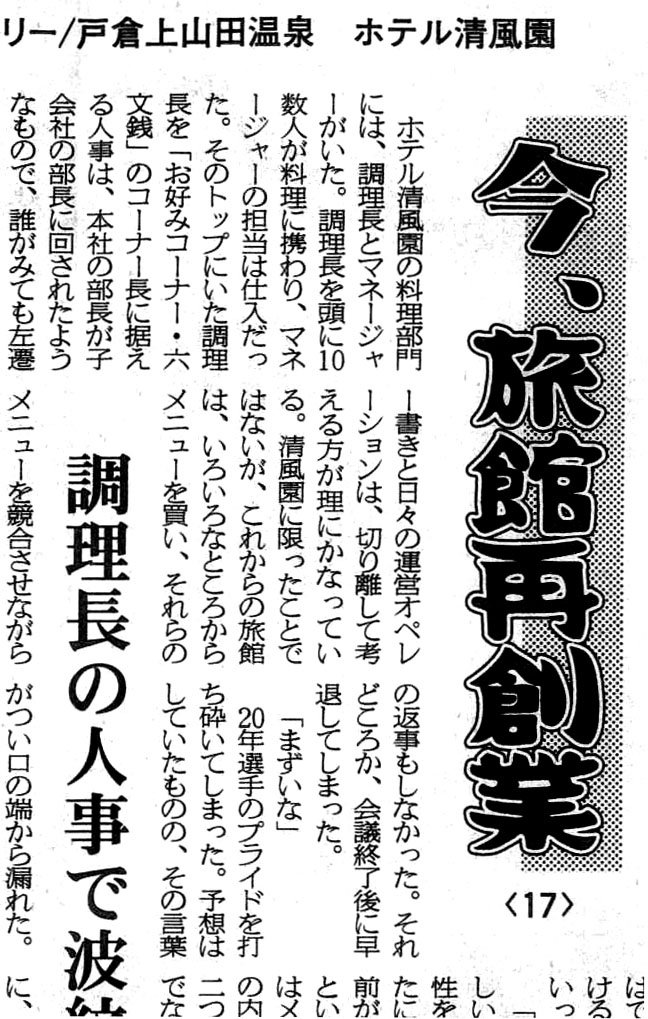 ホテル清風園の料理部門には、調理長とマネージャーがいた。調理長を頭に10数人が料理に携わり、マネージャーの担当は仕入だった。そのトップにいた調理長を「お好みコーナー・六文銭」のコーナー長に据える人事は、本社の部長が子会社の部長に回されたようなもので、誰がみても左遷人事としか思えない。しかし、肩書きを変えても調理長の腕への評価が変ったわけではない。私は彼にいった。
ホテル清風園の料理部門には、調理長とマネージャーがいた。調理長を頭に10数人が料理に携わり、マネージャーの担当は仕入だった。そのトップにいた調理長を「お好みコーナー・六文銭」のコーナー長に据える人事は、本社の部長が子会社の部長に回されたようなもので、誰がみても左遷人事としか思えない。しかし、肩書きを変えても調理長の腕への評価が変ったわけではない。私は彼にいった。
「あなたには、メニュー書きをやってほしい」と。そして、会議でファクトリー運営の説明した。
ファクトリー運営形態をとるとき、料理長のメニュー書きと日々の運営オペレーションは、切り離して考える方が理にかなっている。清風園に限ったことではないが、これからの旅館は、いろいろなところからメニューを買い、それらのメニューを競合させながら料理の幅を広げる必要がある。メニューを書けることが板前の真骨頂であるとすれば、メニューを買うなどはいささか暴論かもしれないが、これくらいの柔軟な発想がないと、変化し多様化を続けるお客様のニーズについていけない。
だが、当の調理長は憮然としたままで、会議では何の返事もしなかった。それどころか、会議終了後に早退してしまった。
「まずいな」
20年選手のプライドを打ち砕いてしまった。予想はしていたものの、その言葉がつい口の端から漏れた。その後、辞める・辞めないの話に発展したのは当然だった。常務の陶山和恒に、私はいった。「自分の道は自分で決めることだが全力で説得しましょう。それだけの腕をもっておられる方なので」と。陶山も説得に乗り出してくれた。
そんな右往左往はあったものの、彼を慰留することはできた。コーナー長を「受ける」といった際に、彼はいった。
「若い者を1人つけてほしい」と。私は、その必要性を認めなかった。「あなたには、いつでも使える板前が10人もいるんですよ」といった。コーナーの横にはメイン厨房がある。仕事の内容こそ違っても、この二つは絶えず連携したものでなければならない。とくに、これからの「六文銭」の〈売り方〉を考えると、食材の仕入をはじめ密接な連携が不可欠だった。
また、再生への基本セオリーは、第1段階として最大限の現状活用と経費削減で利益を生み出し、それを原資にした施設投資で利益を上積みしていくのが第2段階。「六文銭」のリニューアルもこのセオリーに則っていた。コーナー施設の刷新ではなく、メニューのリニューアルで利益を生み出すのが先決だった。コーナー長が彼でなければならない理由が、そこにあった。それは、彼の「顔」と「腕」だった。
かつて、彼はこのコーナーを仕切っていた。評判が非常にいいことから、メイン調理長に据えられた経緯がある。いい選手がいい監督になるとは限らないが、いい選手は「優勝引受人」として切り札的な活躍ができる。プロ野球でも、移籍した年にチームを優勝へ導いた選手がいた。いま、「六文銭」で欲しかったのは、名監督ではなく「切り札選手」だった。
売り方については、コンセプトメーキングの会議を何度も開いた。
「当地では、めったに食べられないような料理を提供する店にしたい」「安売りではなく、高級感がほしい」と議論百出。また、清風園をとりまく立地環境も与件に加えて検討した。ここ戸倉上山田にも温泉地特有の「昼間空洞化」がある。一般市民の多くは域外に職場があり、地元で「帰りに一杯」とはいかないし、適当な店も少ない。「地元に高級感のある店があれば、接待に使ってみたい」といった取引先の声も、そうした実情を表していた。さらに、宿泊部部門の半分は県内客が占めている清風園の実情などを加味すると、「地元客も利用しやすいパブリック施設」との方向が固まった。
8月17日、「高級炉端焼・六文銭」がリニューアルオープンした。告知の折込広告では「玉夫が帰ってきました」と打った。これが奏功した。
(企画設計・松本正憲=文中敬称略)
|
