|
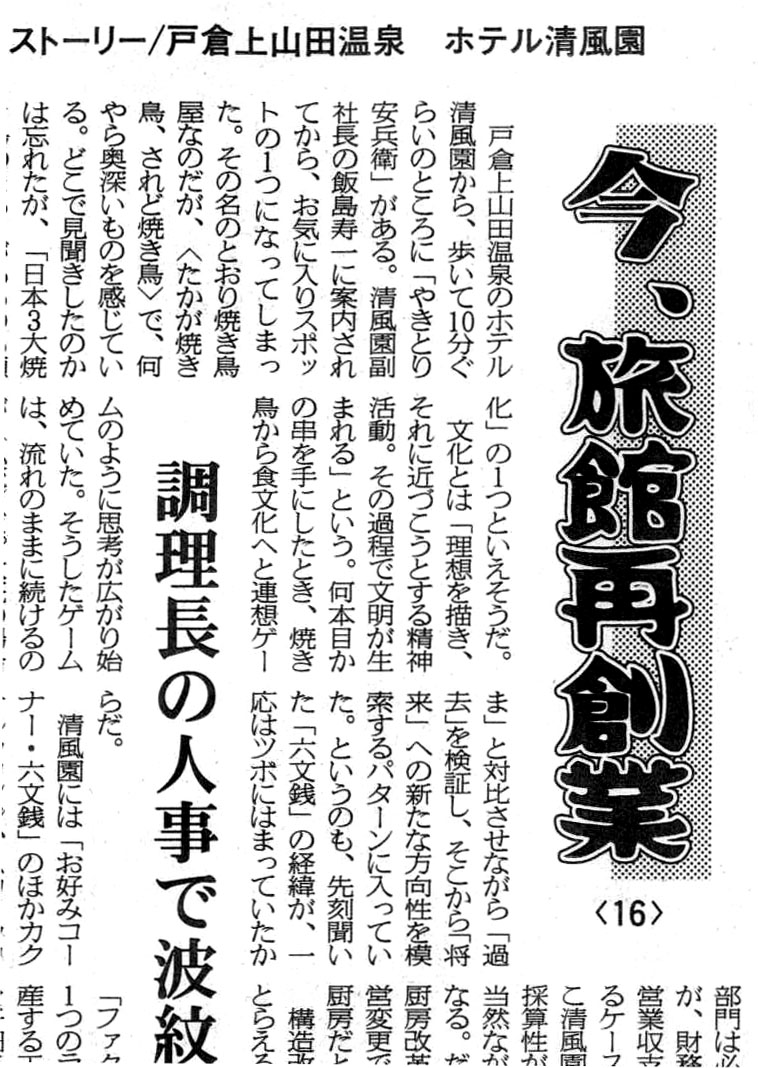 戸倉上山田温泉のホテル清風園から、歩いて10分ぐらいのところに「やきとり安兵衛」がある。清風園副社長の飯島寿一に案内されてから、お気に入りスポットの1つになってしまった。その名のとおり焼き鳥屋なのだが、〈たかが焼き鳥、されど焼き鳥〉で、何やら奥深いものを感じている。どこで見聞きしたのかは忘れたが、「日本3大焼き鳥のまち」があるのも頷ける。室蘭(北海道)、東松山(埼玉県)、今治(愛媛県)がそれで、私の地元である福岡県では留米が「3大まち」に対抗しているとか。ご当地ラーメンと同じように、全国共通の土俵で競い合う「日本の食文化」の1つといえそうだ。
戸倉上山田温泉のホテル清風園から、歩いて10分ぐらいのところに「やきとり安兵衛」がある。清風園副社長の飯島寿一に案内されてから、お気に入りスポットの1つになってしまった。その名のとおり焼き鳥屋なのだが、〈たかが焼き鳥、されど焼き鳥〉で、何やら奥深いものを感じている。どこで見聞きしたのかは忘れたが、「日本3大焼き鳥のまち」があるのも頷ける。室蘭(北海道)、東松山(埼玉県)、今治(愛媛県)がそれで、私の地元である福岡県では留米が「3大まち」に対抗しているとか。ご当地ラーメンと同じように、全国共通の土俵で競い合う「日本の食文化」の1つといえそうだ。
文化とは「理想を描き、それに近づこうとする精神活動。その過程で文明が生まれる」という。何本目かの串を手にしたとき、焼き鳥から食文化へと連想ゲームのように思考が広がり始めていた。そうしたゲームは、流れのままに続けるのが〈私流〉だ。大概の場合いま取組んでいる仕事に収斂するし、思いもよらぬアイデアが閃くこともある。
だが、この日の私は、いつもと違っていた。時間を逆行させる回顧へと思考回路が切り替わっている。「いま」と対比させながら「過去」を検証し、そこから「将来」への新たな方向性を模索するパターンに入っていた。というのも、先刻聞いた「六文銭」の経緯が、一応はツボにはまっていたからだ。
清風園には「お好みコーナー・六文銭」のほかカクテルラウンジ、スカイラウンジ、カラオケルームなどの料飲パブリックがある。今回の運営変更でコーナー部分として最初に取組んだのが「六文銭」だった。というよりも、そうせざるを得ない背景があった。
旅館にとってパブリック部門は必須科目ともいえるが、財務解析をしてみると営業収支が赤字になっているケースが少なくない。ここ清風園もご多分に漏れず採算性が悪い。その改善は、当然ながら1つのテーマとなる。だが、最大の課題は厨房改革にある。逆に、運営変更で一番手こずるのが厨房だともいえる。
構造改革の視点で厨房を捉えると、一口でいえば「ファクトリー」なのだ。1つのライン上でモノを生産する工場といえる
それを仔細にみると、先付けの小鉢、お造りの盛込み、煮物、焼き物、蒸し物とそれぞれのパーツをつくった上で1人前の「膳」に仕上げている。いわばアッセンブリー方式による組立て作業といってもいい。そこには腕の冴えが求められる板前仕事もあれば、短時間で数多くを処理するパートの単純作業もある。ファクトリーの運営は、それらをコントロールするマネジメントの世界なのだ。
ところが、厨房のトップである調理長は、マネジメントよりも「腕」が先行する。腕は「心技一体」の言葉が象徴するように、精神と技術であり、いわば「真―立板―煮方―向板―八寸場―盛付―追いまわし―ぼんさん」といった厳格な縦社会の中で体得するものだ。それを頭から否定することはできないし、逆に彼らの世界では、理論はそれを補完するものでしかない。そこに、現実のマネジメントとの乖離が生じる。
だが、旅館再生の最前線ではマネジメントが何よりも優先される。私は、情など無縁の鬼になる覚悟を決めていた。
厨房改革とパブリック料飲の売上アップ、それとメイン厨房調理長の活用。一石三鳥の狙いでコーナー人事を模索した。それが2カ月以上も前のことだ。コーナー「六文銭」の活性にメイン厨房調理長を投入する。これは、メイン厨房調理長の肩書きを外すことでもあった。全体構想と人事を発表した会議での調理長の顔が、いまも鮮明に脳裏に浮かぶ
(企画設計・松本正憲=文中敬称略)
|

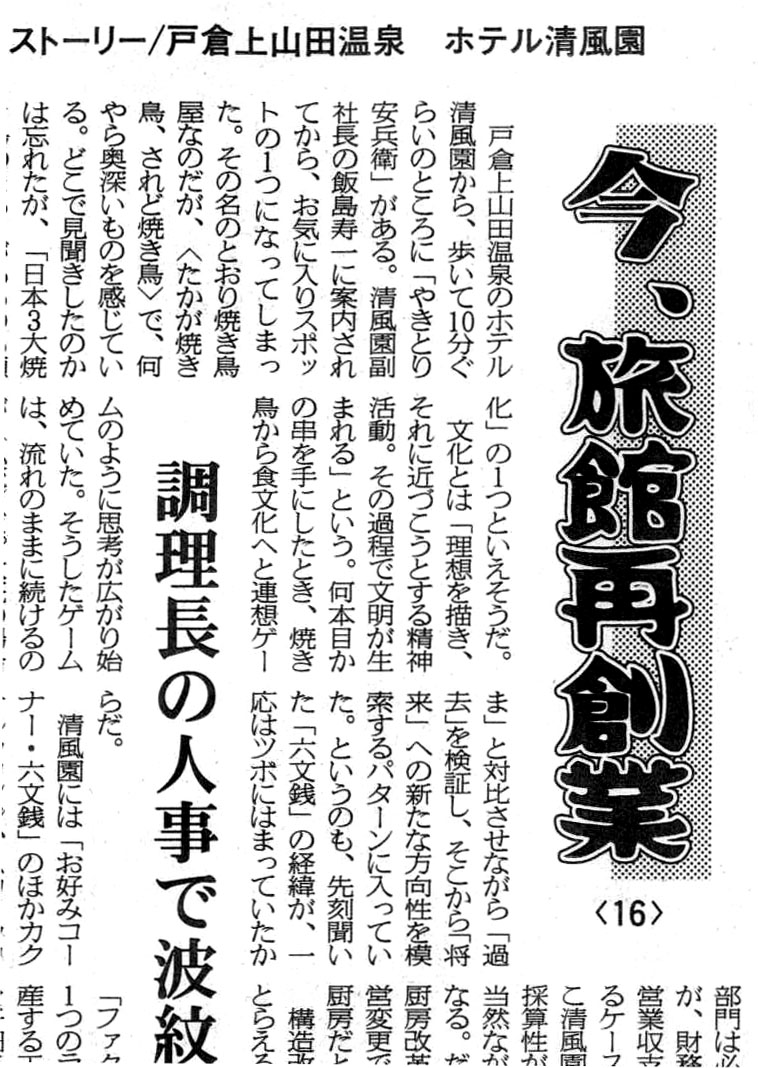 戸倉上山田温泉のホテル清風園から、歩いて10分ぐらいのところに「やきとり安兵衛」がある。清風園副社長の飯島寿一に案内されてから、お気に入りスポットの1つになってしまった。その名のとおり焼き鳥屋なのだが、〈たかが焼き鳥、されど焼き鳥〉で、何やら奥深いものを感じている。どこで見聞きしたのかは忘れたが、「日本3大焼き鳥のまち」があるのも頷ける。室蘭(北海道)、東松山(埼玉県)、今治(愛媛県)がそれで、私の地元である福岡県では留米が「3大まち」に対抗しているとか。ご当地ラーメンと同じように、全国共通の土俵で競い合う「日本の食文化」の1つといえそうだ。
戸倉上山田温泉のホテル清風園から、歩いて10分ぐらいのところに「やきとり安兵衛」がある。清風園副社長の飯島寿一に案内されてから、お気に入りスポットの1つになってしまった。その名のとおり焼き鳥屋なのだが、〈たかが焼き鳥、されど焼き鳥〉で、何やら奥深いものを感じている。どこで見聞きしたのかは忘れたが、「日本3大焼き鳥のまち」があるのも頷ける。室蘭(北海道)、東松山(埼玉県)、今治(愛媛県)がそれで、私の地元である福岡県では留米が「3大まち」に対抗しているとか。ご当地ラーメンと同じように、全国共通の土俵で競い合う「日本の食文化」の1つといえそうだ。