
| 「旅館を黒字にするために」 その30 従業員の「やる気」考える |
Press release |
| 2001.11.17/観光経済新聞 |
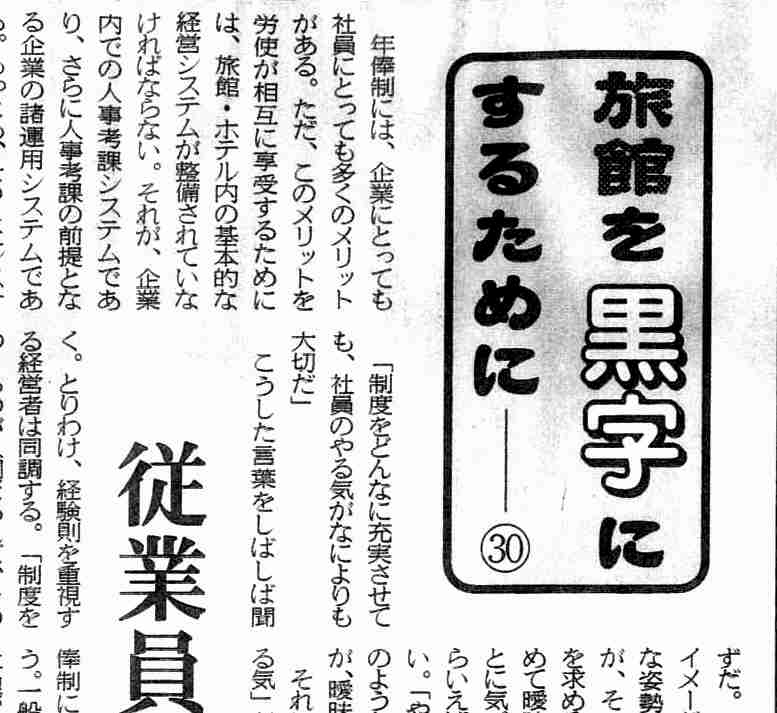 年俸制には、企業にとっても社員にとっても多くのメリットがある。ただ、このメリットを労使が相互に享受するためには、旅館・ホテル内の基本的な経営システムが整備されていなければならない。それが、企業内での人事考課システムであり、さらに人事考課の前提となる企業の諸運用システムである。もっとも、そうしたシステムは、大企業を模した複雑な制度である必要はない。あくまでも、旅館・ホテルの実情に即した形であることが大前提である。
年俸制には、企業にとっても社員にとっても多くのメリットがある。ただ、このメリットを労使が相互に享受するためには、旅館・ホテル内の基本的な経営システムが整備されていなければならない。それが、企業内での人事考課システムであり、さらに人事考課の前提となる企業の諸運用システムである。もっとも、そうしたシステムは、大企業を模した複雑な制度である必要はない。あくまでも、旅館・ホテルの実情に即した形であることが大前提である。ところが、年俸制をはじめとした諸制度を話題にしたとき、おうおうにして問題点がすり替わってしまう。 「制度をどんなに充実させても、社員のやる気がなによりも大切だ」 こうした言葉をしばしば聞く。とりわけ、経験則を重視する経営者は同調する。「制度をつくるのが人間であれば、その下で動くのも人間である。したがって、成否のカギを握るのは、そこにかかわる人間の<やる気>だ」という論である。確かに、システムだけでは人は動かない。言葉自体は否定しないが、そこでいう「やる気」とは何かを考える必要が、一方にあるはずだ。つまり、言葉から伝わるイメージは、少なからぬ前向きな姿勢を感じることもできるが、そこまでである。「やる気」を求める側も応じる側も、きわめて曖昧な要素に満ちていることに気づくはずである。結論からいえば、そこには具体性がない。「やる気」の結果として、どのような「成果」を導き出すかが、曖昧なまま放置されている。 それにもかかわらず、この「やる気」が表面的な形だけで、年俸制に関連付けをされてしまう。一般的な年俸制の仕組みは、社員が自己評価をし、所属する上司の評価、経営トップをはじめとした評価委員会などのクロスチェックを経て決定される。また、今期の実績と来期の予想などが勘案されて算定することから、年功序列を基軸にした定期昇給よりは実情に近い給与体系になる可能性もあるし、何よりも社員が自己評価をすることで「やる気」の動機付けにもなると発想するわけである。そして、いわゆる「目標」を何らかの形で表明することによって、労使ともに「やる気」に安堵してしまう。前号でも若干ふれたが、これでは一カ月の保障が一年に膨らんだだけであり、むしろ活力を削ぐことにもなりかねない。 こうした取り組み姿勢は、年俸制が目的となった導入の姿にほかならない。年俸制は、企業が利益を生み出し、同時に社員が自己の労働対価として給与に満足感を得るための手段の一つなのである。いわば、手段と目的がボーダレス化した結果、本来の意味合いが薄らいでしまう。前号で例示した安易な年俸制によって経営を悪化させたケースでは、発想の根底に「仕事の内容にそぐわない厚遇の給与体系を、年俸制に切り替えることでとりあえず打破しよう」といった発想があった。まさに、「年俸制による目標の自己申告→目標達成への自己努力」といった構図が、導入時点で経営者の意識を支配していたわけだ。 つまり、「なぜ年俸制に切り替えるか」の目的を明確に認識しておく必要がある。結論は前述のように利益確保と社員の満足感をともに果たすためである。その意味で、筆者がたびたび指摘しているように、安易な模倣では目的が達せられないわけである。自館の実情にふさわしい制度化が前提とならざるを得ない。 ただし、冒頭で述べたように、その制度は決して大企業を模した複雑なものである必要はない。むしろ、シンプルでわかりやすい仕組みであることが前提である。例えば、等級制の明確化である。年功ではなく、その仕事のもつ作業の意味合いを「どこまで熟知しているか」、作業内容に対する「速度や正確さ」などを、客観的に量る物差しで「誰に対しても公平に評価しているか」ということである。 余談ではあるが、こうした評価基準に対して、「画一的な基準を充たしていても、現実の場面では利用客に満足を与えられるとは限らない」という反論が出る。論拠は「利用客が感じる満足感は、それこそ十人十色であり、対応する側のキャラクターで変化する場合もある」といったものが多い。そこで、「画一的な評価ではなく個人の裁量を見定めた評価」となり、そこに曖昧性が入り込んでくる。 だが、ここでいう基準とは、各等級で「ここまでは理解し、作業ができる」といった基準であり、その基準を企業側が明示することで、はじめて等級制が生きてくる。労働対価としての満足感が、プラスの効果として働くと筆者は考える。 (続く=経営コンサルタント・松本正憲) |
| (つづく) |