
| 「旅館を黒字にするために」 その11 最終の目標は(売上増) |
Press release |
| 2001.06.30/観光経済新聞 |
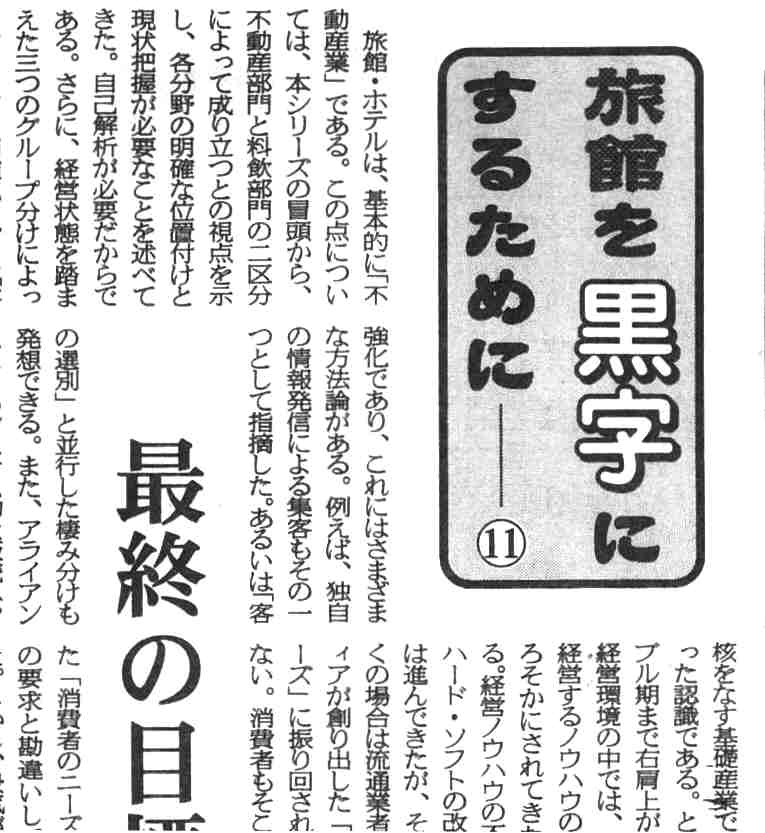 旅館・ホテルは、基本的に「不動産業」である。この点については、本シリーズの冒頭から、不動産部門と料飲部門の二区分によって成り立つとの視点を示し、各分野の明確な位置付けと現状把握が必要なことを述べてきた。自己解析が必要だからである。さらに、経営状態を踏まえた三つのグループ分けによってドメインを明確化し、自ら「客の選別」を行うことで自立再建へ向けた黒字化の途が、今後の選択肢として残されていることも述べた。
旅館・ホテルは、基本的に「不動産業」である。この点については、本シリーズの冒頭から、不動産部門と料飲部門の二区分によって成り立つとの視点を示し、各分野の明確な位置付けと現状把握が必要なことを述べてきた。自己解析が必要だからである。さらに、経営状態を踏まえた三つのグループ分けによってドメインを明確化し、自ら「客の選別」を行うことで自立再建へ向けた黒字化の途が、今後の選択肢として残されていることも述べた。けだし、筆者はこれらの根底をなすものとして「売上をいかに伸ばすか」を最終的な目標と捉えている。いわゆる集客力の強化であり、これにはさまざまな方法論がある。例えば、独自の情報発信による集客もその一つとして指摘した。あるいは「客の選別」と並行した棲み分けも発想できる。また、アライアンスによるシステム的な販売ネットワークの構築も、今後の集客戦略として欠かすことができない。いわば、集客手法を流通業者のみに委ねるのではなく、必要な自助努力を果たす姿勢が不可欠だということである。 こうした考え方の根本は、旅館・ホテルが「観光において中核をなす基礎産業である」といった認識である。ところが、バブル期まで右肩上がりを続けた経営環境の中では、基礎産業を経営するノウハウの醸成が、おろそかにされてきた一面がある。経営ノウハウの不在である。ハード・ソフトの改良や高質化は進んできたが、それとても多くの場合は流通業者やマスメディアが創り出した「消費者のニーズ」に振り回された感が否めない。消費者もそこで創出された「消費者のニーズ」を、自らの要求と勘違いして踊ってきた。しかし、景気が冷え込むにつれて、本音が出てきた。 余談ではあるが、かつて、モツ煮込鍋と焼酎がブームになったことがある。発信地は筆者の本拠地である福岡県だった。これが全国に伝播する過程で「モツ煮込鍋はヘルシー」がキーワードとなり、女性客を引き付けた。もともとは男性客が主体だった居酒屋が、若い女性客の増加で活況を呈す話題の店となり、マスコミにも頻繁に登場するようになった。もちろん、ブームはやがて廃れる。東京都内で雨後のタケノコのように増殖した当時のモツ煮込鍋屋が、いま何件残っているかは筆者の預り知らぬところだが……。 バブル経済が崩壊の兆しを見せ始める前後に、このモツ煮込鍋がブームになった。マスコミの捉え方も若い女性の受けとめ方も、キーワードの「ヘルシー」が前面に据えられていた。しかし、美味さは否定しないが本音は「安さ」にあった。もともと安価な素材であり安く提供できたものが、消費量が増えて売れ筋に変われば、需要と供給の単純な経済理論だけでみても結果はおのずと知れる。そしてブームは去った。今日の発泡酒ブームも同質なものがある。キレや味わいなど表面的なフレーズで消費しているのではなく、やはり安さ以外の何ものでもない。日本酒やウイスキーより安いから焼酎、ビールより安いから発泡酒。供給側(メーカー)は当然ながら、代替品としてではないポリシーがあるはずだが、需要側は本音で対応している。 ここでモツ煮込鍋の盛衰やビール対発泡酒を論じるのは、もとより本旨ではない。要は、ドメインを明確に据えることと、経営ノウハウを確固としたものにつくり上げることである。ひるがえって旅館・ホテルは、確かに施設や料理・サービスといった根幹部分の底上げはなされてきた。外形的な変容を遂げてきたことは、誰もが認めるところであろう。問題は、そうした変容が自らの経営ノウハウに基づくものなのか、単に外的な要因に振り回された結果なのか、ということである。ややもすると、経営ノウハウよりも「借金をする度胸があって建物さえ建てられれば、それなりの経営はやってこられた」という傾向さえ否定できない。これは、ノウハウではないし論外である。筆者は、旅館・ホテルの構造改革に携わり始めた当初、他業界とはまったく異質なこうした現実に直面し、まず驚きを感じたものだった。 では、経営ノウハウとは何か。基本的には自己解析をする内へ向けた能力と、それを収益に反映させる外へ向けた能力を総合したものといえよう。内的には客を選別しうる妥当性をもった経営システムの整備、外的にはアライアンスをはじめとした情報発信による集客力の強化などの形として、具体的に反映させられるものである。例えば、業界の常套語として「施設・料理・サービス」といい慣わされてきたが、本来は「施設」「料理・サービス」を別個に捉え、ドメインの中でそれぞれの位置付けを明確化した対処法が必要なのである。とりわけ、再三指摘している三つのグループ分けにおいては、不動産部門と料飲部門の明確な区分けがカギを握っている。その要は、不動産業としての認識である。 (続く=経営コンサルタント・松本正憲) |
| (つづく) |
