
| 「旅館を黒字にするために」 その6 「価格破壊」に負けぬ経営 |
Press release |
| 2001.05.26/観光経済新聞 |
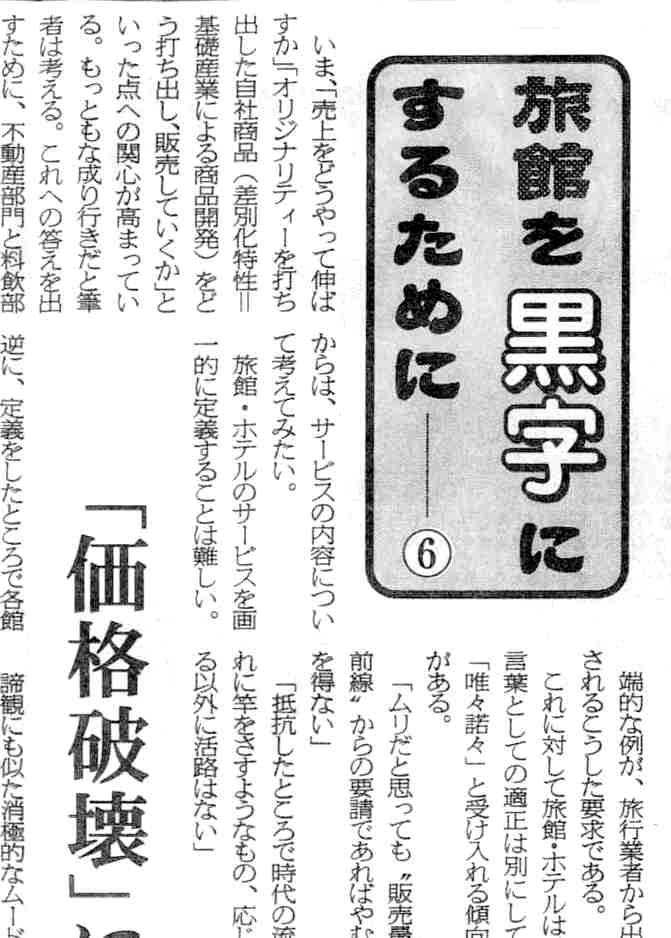 いま、「売上をどうやって伸ばすか」「オリジナリティーを打ち出した自社商品(差別化特性=基礎産業による商品開発)をどう打ち出し、販売していくか」といった点への関心が高まっている。もっともな成り行きだと筆者は考える。これへの答えを出すために、不動産部門と料飲部門を明確に区分したうえでの財務解析の必要性を訴えてきた。
いま、「売上をどうやって伸ばすか」「オリジナリティーを打ち出した自社商品(差別化特性=基礎産業による商品開発)をどう打ち出し、販売していくか」といった点への関心が高まっている。もっともな成り行きだと筆者は考える。これへの答えを出すために、不動産部門と料飲部門を明確に区分したうえでの財務解析の必要性を訴えてきた。その一環として前号では、経営状態による三つのグループ分けを示した。そして、各グループの状況を問わず、いずれの場合でも不動産業を基本に据えながらサービス内容を問い直すことで、現状の客数であっても黒字が出る体質への方向転換が必要なことを強調してきた。今回からは、サービスの内容について考えてみたい。 旅館・ホテルのサービスを画一的に定義することは難しい。逆に、定義をしたところで各館の実情と乖離したものであれば意味がない。むしろ、定義に振り回されて本質を見失う危険性さえはらんでいる。これは、基礎産業として自館の特質を希薄にすることでもある。ところが、現実にはこうした不本意がまかり通っている。 「現状のサービスを維持しながら、消費者の低価格志向に応える価格政策が必要」 端的な例が、旅行業者から出されるこうした要求である。 これに対して旅館・ホテルは、言葉としての適正は別にして「唯々諾々」と受け入れる傾向がある。 「ムリだと思っても"販売最前線"からの要請であればやむを得ない」 「抵抗したところで時代の流れに竿をさすようなもの、応じる以外に活路はない」 諦観にも似た消極的なムードに支配されているようだ。もっとも、これが全てではない。 「永年培ってきた伝統を護るためには、低価格志向であっても経営方針に則ったサービスのレベルは維持する」 「お客さまは、私どものサービスに期待しているのだから、それに応える必要がある」 こうした気骨のある老舗旅館の経営者も少なくはない。これも一理あるし、真っ向から否定するものではないが、ただし条件はつく。「経費増で苦しい」と口にしないことである。どんなに高邁な理念や経営ポリシーがあっても、赤字が前提の企業経営などあり得ないからだ。利益が出ているのならば、そうした気骨は存分に発揮することが望ましい。それは、観光経済新聞でしばしば指摘されてきた「伝統と文化に裏打ちされた旅館の情緒性」を、次代へ伝えるために大きな意味合いをもっている。要は、経営のバランス感覚である。 余談ではあるが筆者は、前シリーズ『旅館の赤字をなくすために』において、「人・モノ・カネ・情報」の経営資源のなかで、「第一にカネと言い切る経営感覚」の重要性を指摘した。企業が企業として成り立つためには、企業活動の根底に黒字経営があり、利益があがってこそ人材育成も設備投資もスムースに運ぶという同然の理を語ったまでである。 前出の唯々諾々とした対応、気骨のある対応、そのどちらにおいても、黒字経営ならば問題はない。だが、現実には逆である。そうした対応が経営の足を引っ張っていることは、改めて述べるまでもない。 では、問題点はどこにあるのか。筆者は、本シリーズにおいて不動産部門と料飲部門の財務解析の重要性を指摘し続けている。つまり、建築コストや稼働率を想定したうえで客室の標準価格を決め、さらに料飲部門の運営費(人件費・原価・諸オペレーションコスト)が加算されて最終的な販売価格が決定されているはずだ。ところが、バブル経済が弾けた後の低価格志向によって、そうして算出された販売価格は崩れている。結局、悪循環のループに陥ってしまい、歯止めを見つけられないまま状況に流されている。 こうした現状は、視点を換えると二つのことがいえる。第一は、最終的に積算されたはずの販売価格の内実が、合理的な妥当性に裏打ちされていない。非合理とはいわないまでも、あいまいなまま見過ごされてきた部分が少なからずある。 第二は、価格破壊が進むなかで、どれくらいまで下げたらいいのかが把握されていな。限りなく下げ続けるなどは、どだいできる相談ではない。まして、現状のサービス水準を維持しながらとなると、一方的な"ないものねだり"の感さえある。 「どこまで価格破壊が進むのか。これ以上の値下げは経営を危うくする」 こうした声がマジョリティーになっている現状下での自力再建は、不動産・料飲両部門の大枠としての財務解析と、各部門での現実に見合った改革が不可欠である。 (続く=経営コンサルタント・松本正憲) |
| (つづく) |