
| 「旅館を黒字にするために」 その2 自らに主体を置いた経営 |
Press release |
| 2001.04.21/観光経済新聞 |
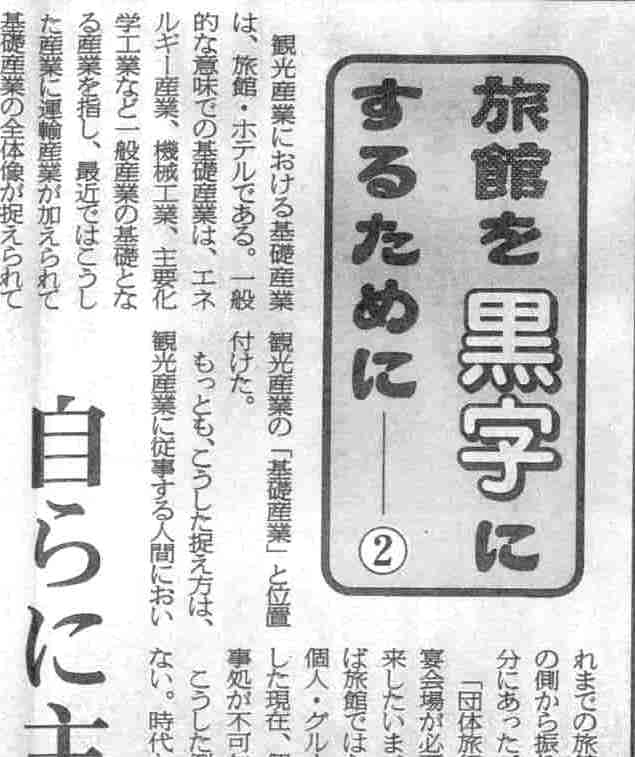 観光産業における基礎産業は、旅館・ホテルである。一般的な意味での基礎産業は、エネルギー産業、機械工業、主要化学工業など一般産業の基礎となる産業を指し、最近ではこうした産業に運輸産業が加えられて基礎産業の全体像が捉えられている。
観光産業における基礎産業は、旅館・ホテルである。一般的な意味での基礎産業は、エネルギー産業、機械工業、主要化学工業など一般産業の基礎となる産業を指し、最近ではこうした産業に運輸産業が加えられて基礎産業の全体像が捉えられている。ひるがえって観光産業をみると、とりわけ一般的な宿泊旅行の商品化では、旅館・ホテル、輸送機関、食事・休憩施設が人為的要素の加わった素材として核をなしている。なかでも旅館・ホテルは、消費者が旅行意思を決定する要素としての意味合いを含めて、最も大きなファクターといえる。そこで筆者は、旅館・ホテルを観光産業の「基礎産業」と位置付けた。 もっとも、こうした捉え方は、観光産業に従事する人間においては既定の事実として広く認識されているはずであり、「いまさら」のそしりを受けかねない。だが、再確認の意味を含めてあえて提言しているのは、その基礎産業としての認識が、旅館・ホテルの経営姿勢において十二分に反映されているとはいい難い状況に、しばしば出会うからである。 もって回ったいい方になってしまったが、端的にいえば、これまでの旅館・ホテルは流通業の面から振り回される傾向が多分にあった。 「団体旅行に対応するには大宴会場が必要」「温泉ブームが到来したいま、露天風呂がなければ旅館ではない」「団体旅行から個人・グループ旅行へと多様化した現在、個人客に対応した食事処が不可欠」 こうした例は枚挙にいとまがない。時代とともに変化するニーズに向けて、そのつど旅館・ホテルは施設をリニューアルし、莫大な投資をそれぞれの施設が実施してきた。形のうえで「ハード面」に走ってきたわけだが、一方でサービスの質的向上にも同様に対応してきた。「ソフト面」の充実ともいわれたそれらの対応施策は、ハード面のリニューアルとある意味で連動していた。「施設のグレードに見合ったサービスの提供」と位置付けられていた。 こうしたニーズへの対応自体は、もとより必要なものであると筆者は認識している。問題は、そうしたニーズを自ら検証し、自館の施設へどう反映させてきたかである。大宴会場も露天風呂も食事処も、逆説的にいえば、それを作ったことで客が増加し、その後の黒字経営につながったのかとの問題がある。客が増えても、投資を回収する前に次の投資を必要とする事態の発生が、これまでの経緯ではなかったかと考えられる。結果として、売上は伸びていても収益面でみると恒常的な赤字体質に陥ったのではないか。 そこに、旅館・ホテルのマーケティング手法やマネジメント能力に何らかの問題点があると考えざるを得ない。 例えば、前号で指摘した人件費もその一つである。前述の「施設のグレードに見合ったサービスの提供」といったそれ自体に必然性はあっても、その前にニーズ対応の名目から「ハード面」へ走った事実を、マーケティングとマネジメントの視点でどこまで検証していたかである。 結論からいえば、マーケティングにおいて自館の実情を含めて可能な限りの検証をしたのか。マネジメントにおいて部屋あるいは施設と料飲の関係を、どう位置付けて経営に反映させていたのか。こうした視点は、かなり希薄ではなかったかと推測できる。換言すれば、赤字を引き起こす要因が、そこに潜んでいたといえる。 これに対して、マーケティング面での答えは、「流通業者からのリクエストは、消費者への販売窓口で吸い上げたニーズの反映」といった認識の仕方で取り入れる傾向が強かった。確かに、それは販売の多くを流通業者に委ねている以上、当然ともいえる答えだが、一方でマネジメント面ではどうなのかとの疑問がわく。 つまり、流通業者が販売をする上で何らかの思惑が含まれていると、結果として思惑に踊らされることになる。例えば、通常の大浴場だけでは競合他社商品との差別かが図れない。そこで、露天風呂を加えた方が目新しく「売りやすい」ことから、消費者のニーズは「露天風呂に向かっている」となる。これは、決してうがち過ぎとはいえない一面がある。 筆者は、これらを全否定する気は毛頭ない。ただ、観光の基礎産業である以上、主体を自らにおいたニーズの把握と自館の実情にあった反映手法は、自ら構築すべきだと考える。それが自力再建の途であり、基礎産業と捉えるゆえんでもある。 (続く=経営コンサルタント・松本正憲) |
| (つづく) |